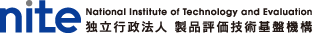
|
|
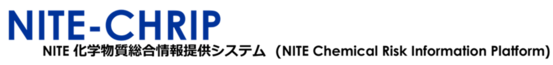
|
 NITEトップ>
化学物質管理分野>
NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)
NITEトップ>
化学物質管理分野>
NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)
|
|
|
NITE-CHRIP(ナイトクリップ)では国内外における
化学物質の法規制・有害性情報等を提供しています
|
検索結果;検索結果(物質の情報)画面の使い方
選択した物質(CHRIP_ID)に該当する情報がツリー形式で表示されます。
通常はデータのある項目のみ表示します。該当データがない項目も表示する場合は「データのない情報源を含めて表示」のタグをクリックして下さい。
情報の表示
情報源の情報が表示され、データの説明や関連サイトを別画面で表示したり、ツリーの展開、閉塞を行うことができます。
| ツリー項目 | 動作説明 |
| 「-」ボタン | ボタンをクリックすると、下位項目が閉塞します。 |
| 「+」ボタン | ボタンをクリックすると、下位項目が展開します。 |
| データの説明リンク | 「データの説明」リンクをクリックすると、情報源に関する説明を別画面で表示します。 |
| 関連サイトリンク | リンクをクリックすると、関連サイトを別画面で表示します。 ※情報源に設定により、表示されない場合があります。 |
検索結果のダウンロード
「検索結果をダウンロード」のリンクをクリックすると、検索結果の一覧をTSV形式(タブ区切り形式)でダウンロードできます。TSV形式でのファイルの開き方についてはこちらを参照してください。
一般情報
一般情報
CHRIP_ID
NITE-CHRIPが付与している番号です。
CAS登録番号(CAS RN)
アメリカ化学会の機関であるCAS(Chemical Abstracts Service)が個々の化学物質もしくは化学物質群に付与している登録番号です。
日本語名
日本語名又はCAS登録番号(CAS RN)に関連する物質の日本語名が表示されます。CAS登録番号(CAS RN)が表示されていない場合は当該物質の日本語名が表示されます。
英語名
CAS登録番号(CAS RN)に対応する英語名又はCAS登録番号(CAS RN)に関連する物質の英語名が表示されます。CAS登録番号(CAS RN)が表示されていない場合は当該物質の英語名が表示されます。
分子式
物質の分子式又は組成式等が表示されます。
分子量
物質の分子量が表示されます。
SMILES
物質のSMILESが表示されます。 このSMILESは、ChemDrawで作成されたものです。
構造式
CAS登録番号(CAS RN)に対応する物質の構造式が表示されます。CAS登録番号(CAS RN)に対応する物質で構造が複数ある場合は代表例を示している場合があります。CAS登録番号(CAS RN)で構造が特定できない場合であっても、混合物等の代表例を示している場合があります。
別名
日本語名、英語名の別名が表示されます。
別名がNITE-CHRIPに登録されていない場合は、この項目自体が表示されません。
別名がNITE-CHRIPに登録されていない場合は、この項目自体が表示されません。
CAS RNに関する注記
データの掲載日:2024.03.12
Chemical Abstracts Service(CAS)が実施するCAS Registry Numbers®(CAS RN®)*
ライセンスプログラムの検証結果に関する情報を掲載しています。
*CAS RN®は、米国化学会の知的財産であり、CASの明示的な許可を得て National Institute of Technology & Evaluationが使用しています。
*CAS RN®は、米国化学会の知的財産であり、CASの明示的な許可を得て National Institute of Technology & Evaluationが使用しています。
注記
検証の結果に関する情報が表示されます。

| CAS RNが他のCAS RNに置換されている場合、以下の例のとおり表示されます。 (例)CAS RN AがCAS RN Bに置換されている場合 CAS RN A:このCAS RNはCAS RN Bに置換された。 CAS RN B:置換前のCAS RNはCAS RN Aである。 |
| 優先的に使用するCAS RNがある場合、以下の例のとおり表示されます。 (例)CAS RN AとCAS RN Bは同じ物質だが、CAS RN Aが優先的に使用される場合 CAS RN A:優先CAS RNはCAS RN Aである。 CAS RN B:優先CAS RNはCAS RN Aであり、CAS RN Bは非優先CAS RNである。 |
| 化学物質索引の過程でCAS RNが誤って作成され、その後削除された場合等においては、以下の例のとおり表示されます。 (例)このCAS RNは削除され、かつ、他のCAS RNに置換されていない。 |
| 化学物質索引は行われておらず、CAS RNが欠番となっている場合には、以下の例のとおり表示されます。 (例)このCAS RNは存在せず、無効である可能性がある。 |
| CAS RNの検証が実施されていない場合は、以下の例のとおり表示されます。 (例)このCAS RNはCASによって検証されておらず、不正確である可能性がある。 |
備考
備考が表示されます。
日本化学物質辞書(日化辞)情報
データ掲載日:2024.03.12
「日本化学物質辞書(日化辞)」は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営する科学技術情報(研究者、文献、特許、研究課題、機関、科学技術用語、化学物質、遺伝子、資料、研究資源)を統合的に検索できるサービス「J-GLOBAL」により提供されている有機化合物データベースです。化合物の名称(日本語、英語表記)、分子式、分子量、法規制番号、化学構造などを収録しています。
日化辞番号
日本化学物質辞書における物質固有の番号です。
日化辞詳細情報
J-GLOBALの日本化学物質辞書の該当する物質のページにリンクします。
用途
データ掲載日:2011.04
用途は、産業や消費生活製品などにおける化学物質の利用目的について、引用した出典ごとにその情報をまとめたものです。
NITE-CHRIPでは、化学物質の用途情報を出典又は情報源ごとに表示しています。なお、農薬に関して、農薬取締法において過去に農薬としての登録がされていたが登録の更新がなされていないものは失効農薬として、その旨を括弧内に記載しています。
NITE-CHRIPでは、化学物質の用途情報を出典又は情報源ごとに表示しています。なお、農薬に関して、農薬取締法において過去に農薬としての登録がされていたが登録の更新がなされていないものは失効農薬として、その旨を括弧内に記載しています。
用途
情報収集を行った化学物質の用途について記載していますが、それらの化学物質の用途については記載されていない他の用途もあり得ます。
なお、用途の記載順は、必ずしも化学物質の使用量等の順となっていません。また、出典又は情報源の情報に一部修正を加えている場合があります。
なお、用途の記載順は、必ずしも化学物質の使用量等の順となっていません。また、出典又は情報源の情報に一部修正を加えている場合があります。
出典
用途情報の引用元を表記しています。引用元については以下のとおりです。
・化学工業日報社:株式会社化学工業日報社新化学インデックス2008年版、15107の化学商品
・NITE初期リスク評価書:NITEが関係機関と協力して作成した初期リスク評価書
・NITE調査:国の公開情報、工業団体及び企業のWEBサイト、ハンドブック等をNITEが独自調査したもの
・化学工業日報社:株式会社化学工業日報社新化学インデックス2008年版、15107の化学商品
・NITE初期リスク評価書:NITEが関係機関と協力して作成した初期リスク評価書
・NITE調査:国の公開情報、工業団体及び企業のWEBサイト、ハンドブック等をNITEが独自調査したもの
備考
用途情報について参考となる情報を記載しています。
国内法規制情報
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
化審法:第一種特定化学物質
データ掲載日:2024.03.12 (2023.12.01公布、2024.02.01施行)
難分解性かつ高濃縮性であり、人又は高次捕食動物に対する長期毒性を有するおそれがあり、政令(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条)により定められた物質です。 第一種特定化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
政令番号
第一種特定化学物質として政令により定められた際に付与された番号です。
官報公示日
第一種特定化学物質として官報により公示された日です。
政令施行日
第一種特定化学物質として政令により定められた日です。
政令名称
第一種特定化学物質として政令により定められた際の名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)
へリンクします。
化審法:第二種特定化学物質
データ掲載日:2017.03.21 (1990.09.12公示)
人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で、政令(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第二条)により定められた物質です。 第二種特定化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
政令番号
第二種特定化学物質として政令により定められた際に付与された番号です。
政令施行日
第二種特定化学物質として政令により定められた日です。
政令名称
第二種特定化学物質として政令により定められた際の名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:監視化学物質
データ掲載日:2023.07.31 (2018.04.02公示)
難分解性かつ高濃縮性であり、人又は高次捕食動物に対する長期毒性が明らかでない化学物質で、法第二条第四項の規定に基づき公示された物質です。 監視化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
通し番号
監視化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
官報公示日
監視化学物質として官報に公示された日です。
化審法官報整理番号
官報に公示された際に付与された番号で、1桁の類別番号と4桁の通し番号から構成されています。
官報公示名称
監視化学物質として官報に公示された名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:優先評価化学物質
データ掲載日:2024.01.30(2023.04.01指定)
人又は生活環境動植物への長期毒性を有しないことが明らかであるとは認められず、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあり、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがないと認められないため、そのおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある物質で、化審法第二条第五項の規定に基づき公示された物質です。 優先評価化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
通し番号
優先評価化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
指定日
優先評価化学物質として指定された日です。
化審法官報整理番号
官報に公示された際に付与された番号で、1桁の類別番号と4桁の通し番号から構成されています。
官報公示名称
優先評価化学物質として官報に公示された名称です。
指定の根拠
優先評価化学物質に指定された観点で、人健康影響と生態影響の該当観点が表示されます。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:(取消)優先評価化学物質
データ掲載日:2023.11.28(2023.03.31公示)
優先評価化学物質として指定された物質のうち、リスク評価の結果等に基づき優先評価化学物質としての指定が取り消された物質です。(取消)優先評価化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
通し番号
優先評価化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
取消日
優先評価化学物質の指定が取消された日です。
化審法官報整理番号
官報に公示された際に付与された番号で、1桁の類別番号と4桁の通し番号から構成されています。
優先評価化学物質指定日
優先評価化学物質として官報に公示された日です。
官報公示名称
優先評価化学物質として官報に公示された名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
取消に関する注記
指定を取り消された化学物質が新たに指定された優先評価化学物質に包含される場合、包含先の優先評価化学物質の通し番号及び官報公示名称が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:新規公示化学物質(2011年4月1日以降届出)
データ掲載日:2023.10.03(2023.07.31公示)
我が国で新たに製造又は輸入される化学物質として、2011年4月1日以降に届け出られたもののうち、第一種特定化学物質に該当しないものと判定され、法第四条第四項に基づき、2017年以降に公示された物質です。
第二条第七項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。新規公示化学物質(2011年4月1日以降届出)に該当する場合、以下の項目が表示されます。
通し番号
新規化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
官報公示日
上記の新規化学物質として官報に公示された日です。
化審法官報整理番号
官報に公示された際に付与された番号で、1桁の類別番号と4桁の通し番号から構成されています。
類別
化審法官報整理番号は9種類に分類されており、1類~9類のいずれかが表示されます。
|
第1類 |
無機化合物 |
|
第2類 |
有機鎖状低分子化合物 |
|
第3類 |
有機炭素単環低分子化合物 |
|
第4類 |
有機炭素多環低分子化合物 |
|
第5類 |
有機複素環低分子化合物 |
|
第6類 |
有機重合系高分子化合物 |
|
第7類 |
有機縮合系高分子化合物 |
|
第8類 |
化工でん粉、加工油脂等の有機化合物 |
|
第9類 |
構造不明等化合物 |
官報公示名称
上記の新規化学物質として官報に公示された名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:新規公示化学物質(2011年3月31日以前届出)
データ掲載日:2024.03.12(2016.07.29公示)
我が国で新たに製造又は輸入される化学物質として、2011年3月31日以前に届け出られたもののうち、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質のいずれにも該当しないものと判定され、法第四条第四項に基づき、2016年以前に公示された物質です。
第二条第七項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。新規公示化学物質(2011年3月31日以前届出)に該当する場合、以下の項目が表示されます。
通し番号
新規化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
官報公示日
上記の新規化学物質として官報に公示された日です。
化審法官報整理番号
官報に公示された際に付与された番号で、1桁の類別番号と4桁の通し番号から構成されています。
類別
化審法官報整理番号は9種類に分類されており、1類~9類のいずれかが表示されます。
|
第1類 |
無機化合物 |
|
第2類 |
有機鎖状低分子化合物 |
|
第3類 |
有機炭素単環低分子化合物 |
|
第4類 |
有機炭素多環低分子化合物 |
|
第5類 |
有機複素環低分子化合物 |
|
第6類 |
有機重合系高分子化合物 |
|
第7類 |
有機縮合系高分子化合物 |
|
第8類 |
化工でん粉、加工油脂等の有機化合物 |
|
第9類 |
構造不明等化合物 |
官報公示名称
上記の新規化学物質として官報に公示された名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
労働安全衛生法公表化学物質に関する注記
昭和54年2月5日の告示に基づき、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質及び日本薬局方第8改正(昭和46年)に収載された物質は安衛法においても既存化学物質として取り扱われます。これらの物質については本注記に「昭和54年6月29日までに化審法の規定により公示された化学物質」と記載されます。
労働安全衛生法公表化学物質に関する詳細情報
労働安全衛生法の詳細情報がある場合、厚生労働省の「職場の安全サイト」へリンクします。
化審法:既存化学物質
データ掲載日:2024.03.12 (1974.05.14公示)
1973(昭和48)年の化審法の公布の際、現に業として製造又は輸入されていた化学物質(試験研究のために製造され又は輸入されていた化学物質及び試薬として製造され又は輸入されていた化学物質を除く)であり、化審法の規定により名称が公示された化学物質(既存化学物質名簿に記載されている化学物質)です。現行化審法においては、第二条第七項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。既存化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
化審法官報整理番号
官報に公示された際に付与された番号で、1桁の類別番号と4桁の通し番号から構成されています。
類別
化審法官報整理番号は9種類に分類されており、1類~9類のいずれかが表示されます。
|
第1類 |
無機化合物 |
|
第2類 |
有機鎖状低分子化合物 |
|
第3類 |
有機炭素単環低分子化合物 |
|
第4類 |
有機炭素多環低分子化合物 |
|
第5類 |
有機複素環低分子化合物 |
|
第6類 |
有機重合系高分子化合物 第6類の用語の定義 【PDF:39KB】 |
|
第7類 |
有機縮合系高分子化合物 第7類の用語の定義 【PDF:77KB】 |
|
第8類 |
化工でん粉、加工油脂等の有機化合物 |
|
第9類 |
医薬等の化合物 |
官報公示名称
既存化学物質名簿(官報公示)に記載された名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
労働安全衛生法公表化学物質に関する注記
昭和54年2月5日の告示に基づき、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質及び日本薬局方第8改正(昭和46年)に収載された物質は安衛法においても既存化学物質として取り扱われます。これらの物質については本注記に「昭和54年6月29日までに化審法の規定により公示された化学物質」と記載されます。
労働安全衛生法公表化学物質に関する詳細情報
労働安全衛生法の詳細情報がある場合、厚生労働省の「職場の安全サイト」へリンクします。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:旧第二種監視化学物質
データ掲載日:2024.03.12 (2011.03.22公示)
人への長期毒性を有するおそれがある疑いのある化学物質で、2011(平成23)年4月1日より前に指定化学物質又は第二種監視化学物質として公示された物質です。なお、2005(平成17)年3月2日までに公示された指定化学物質は、法改正により第二種監視化学物質とみなすとされているため、NITE-CHRIPでは旧第二種監視化学物質として表示しております。
現行化審法においては、第二条第七項の規定に基づき一般化学物質に指定されています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。 旧第二種監視化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
現行化審法においては、第二条第七項の規定に基づき一般化学物質に指定されています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。 旧第二種監視化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
通し番号
旧二種監視化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
官報公示日
旧二種監視化学物質として官報に公示された日です。
化審法官報整理番号
化審法官報整理番号がある場合その番号が表示されます。
官報公示名称
旧二種監視化学物質として官報に公示された名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:旧第三種監視化学物質
データ掲載日:2024.01.30 (2011.03.22公示)
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質で、2011(平成23)年4月1日より前に第三種監視化学物質として公示された物質です。
現行化審法においては、第二条第七項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。 旧第三種監視化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
現行化審法においては、第二条第七項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。 旧第三種監視化学物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
通し番号
旧三種監視化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
官報公示日
旧三種監視化学物質として官報に公示された日です。
化審法官報整理番号
化審法官報整理番号がある場合その番号が表示されます。
官報公示名称
旧三種監視化学物質として官報に公示された名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:製造輸入量の届出を要しない物質
データ掲載日:2024.01.30(2023.03.31公示)
第一種特定化学物質、第二種特定化学物質のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価を行うことが必要と認められないものとして、化審法の規定に基づき公示された物質です。 製造輸入量の届出を要しない物質に該当する場合、以下の項目が表示されます。
類別
製造輸入量の届出を要しない物質が官報に公示された際の類別です。
|
第1類 |
無機化合物 |
|
第2類 |
有機鎖状低分子化合物 |
|
第3類 |
有機炭素単環低分子化合物 |
|
第4類 |
有機炭素多環低分子化合物 |
|
第5類 |
有機複素環低分子化合物 |
|
第6類 |
有機重合系高分子化合物 |
|
第7類 |
有機縮合系高分子化合物 |
|
第8類 |
化工でん粉、加工油脂等の有機化合物 |
|
第9類 |
医薬等の化合物 |
化審法官報整理番号
製造輸入量の届出を要しない物質として官報に公示された化審法官報整理番号です。
官報公示日
現在の製造輸入量の届出を要しない物質リストが官報に公示された日です。
官報公示名称
化審法官報整理番号に該当する公示名称です。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
化審法:新規化学物質として取り扱わない物質
データ掲載日:2024.01.30
厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長の連名で、2011(平成23)年3月31日に公表されている通知、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の規定により「新規化学物質として取り扱わないものとする」とされているものです。 「新規化学物質として取り扱わない物質」に該当する場合、以下の項目が表示されます。
法規制分類
「新規化学物質として取り扱わない」旨表示されます。
根拠となる化審法官報公示整理番号
根拠として参照される官報公示整理番号が表示されます。
備考
CAS登録番号(CAS RN)の範囲が該当物質以外を含む場合にその該当条件が表示されます。
詳細情報
詳細情報がある場合、
化審法データベース(J-CHECK)へリンクします。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)
化管法は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、の略称で、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的として、1999(平成11)年に制定された法律です。
化管法:第一種指定化学物質は、人の健康を損なうおそれや動植物の生息等に支障を及ぼすおそれ、オゾン層の破壊等のおそれのあるもののうち、物理的化学的性状や製造、輸入、使用等の状況からみて、相当広範囲な地域の環境において継続して存在すると認められるもので、化管法第二条第二項に基づき、同法施行令第一条で指定された化学物質です。
化管法:第二種指定化学物質は、製造量・輸入量又は使用量の増加等により、第一種指定化学物質の要件と同等となることが見込まれるもので、化管法第二条第三項に基づき、同法施行令第二条で指定された化学物質です。
2008年11月21日、2021年10月20日の政令改正により、指定化学物質の見直しが行われました。
*旧指定化学物質:第一種354物質(特定第一種12物質)、第二種81物質(2000年3月29日政令公布)
*現指定化学物質:第一種462物質(特定第一種15物質)、第二種100物質(2008年11月21日政令改正)
*新規指定化学物質:第一種515物質(特定第一種23物質)、第二種134物質(2021年10月20日政令改正)
なお、届出の対象物質が金属等の場合、元素に換算する必要があります。換算係数等一覧(令和4年度以前)及び換算係数等一覧(令和5年度以降)をご参照ください。
化管法:第一種指定化学物質は、人の健康を損なうおそれや動植物の生息等に支障を及ぼすおそれ、オゾン層の破壊等のおそれのあるもののうち、物理的化学的性状や製造、輸入、使用等の状況からみて、相当広範囲な地域の環境において継続して存在すると認められるもので、化管法第二条第二項に基づき、同法施行令第一条で指定された化学物質です。
化管法:第二種指定化学物質は、製造量・輸入量又は使用量の増加等により、第一種指定化学物質の要件と同等となることが見込まれるもので、化管法第二条第三項に基づき、同法施行令第二条で指定された化学物質です。
2008年11月21日、2021年10月20日の政令改正により、指定化学物質の見直しが行われました。
*旧指定化学物質:第一種354物質(特定第一種12物質)、第二種81物質(2000年3月29日政令公布)
*現指定化学物質:第一種462物質(特定第一種15物質)、第二種100物質(2008年11月21日政令改正)
*新規指定化学物質:第一種515物質(特定第一種23物質)、第二種134物質(2021年10月20日政令改正)
なお、届出の対象物質が金属等の場合、元素に換算する必要があります。換算係数等一覧(令和4年度以前)及び換算係数等一覧(令和5年度以降)をご参照ください。
化管法(令和4年度分までの排出量等の把握や令和4年度末までのSDS提供の対象)
データ掲載日:2023.07.31 (2008.11.21公布)
分類
以下のいずれかが表示されます。
|
第一種 |
第一種指定化学物質に該当します。第一種指定化学物質を扱う事業者には、排出量等の届出(PRTR)及びこの物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際 に性状及び取扱い等に関する情報(化学物質等安全データシート;SDS)の提供が義務化されています。 |
|
第二種 |
第二種指定化学物質に該当します。第二種指定化学物質を扱う事業者には、この物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際に化学物質等安全データシート(SDS)の提供が義務化されています。 |
|
特定第一種 |
特定第一種指定化学物質に該当します。第一種指定化学物質の中で、ヒトへの発がん性を有する物質として定められているものです。第一種指定化学物質よりも排出量の届出要件が厳しく定められています。 |
政令番号
政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
化学物質選定根拠
薬事・食品審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保険部会PRTR対象物質等専門委員会の合同会合において、第一種及び第二種指定化学物質の見直しの根拠としたデータ(平成24年度経済産業省請負調査研究「化管法対象物質に関する有害性情報等の整備事業」)へリンクします。
リンク
当センターから公開しているPRTRマップへのリンクです。排出量マップ、大気濃度マップが公開されている場合、それぞれのマップにリンクしています。
化管法(令和5年度分以降の排出量等の把握や令和5年度以降のSDS提供の対象)
データ掲載日:2023.07.31 (2021.10.20公布)
管理番号
化管法の1指定化学物質に対応する固有の番号です。令和6年度のPRTR届出(令和5年度排出量等把握分)からは管理番号をご利用いただく予定です。
分類
以下のいずれかが表示されます。
|
第一種 |
第一種指定化学物質に該当します。第一種指定化学物質を扱う事業者には、排出量等の届出(PRTR)及びこの物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際 に性状及び取扱い等に関する情報(化学物質等安全データシート;SDS)の提供が義務化されています。 |
|
第二種 |
第二種指定化学物質に該当します。第二種指定化学物質を扱う事業者には、この物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際に化学物質等安全データシート(SDS)の提供が義務化されています。 |
|
特定第一種 |
特定第一種指定化学物質に該当します。第一種指定化学物質の中で、ヒトへの発がん性を有する物質として定められているものです。第一種指定化学物質よりも排出量の届出要件が厳しく定められています。 |
政令番号
政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
化学物質選定根拠
薬事・食品審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保険部会PRTR対象物質等専門委員会の合同会合において、第一種及び第二種指定化学物質の見直しの根拠としたデータ(平成24年度経済産業省請負調査研究「化管法対象物質に関する有害性情報等の整備事業」)です。リンクが表示されている場合、そのデータへリンクします。
リンク
当センターから公開しているPRTRマップへのリンクです。排出量マップ、大気濃度マップが公開されている場合、それぞれのマップにリンクしています。
労働安全衛生法(安衛法)
安衛法:名称公表化学物質/新規名称公表化学物質
データ掲載日:2024.03.12(2023.12.27公示)
安衛法の既存物質は下記2種類に分けてリスト化しています。
(1)安衛法:名称公表化学物質:労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により、労働大臣がその名称等を公表した化学物質(昭和54年6月29日までに国内で製造・輸入され、官報に公示された物質)です。
(2)安衛法:新規名称公表化学物質:労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定により、厚生労働大臣が名称等を公表した新規化学物質(昭和54年6月30日以降に労働安全衛生法の新規化学物質として届け出され、官報に公示された物質)です。
なお、昭和54年2月5日の告示に基づき、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質及び日本薬局方第8改正(昭和46年)に収載された物質は安衛法においても既存化学物質として取り扱われます。これらの物質については化審法の欄の「労働安全衛生法公表化学物質に関する注記」に記載されています。
(1)安衛法:名称公表化学物質:労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により、労働大臣がその名称等を公表した化学物質(昭和54年6月29日までに国内で製造・輸入され、官報に公示された物質)です。
(2)安衛法:新規名称公表化学物質:労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定により、厚生労働大臣が名称等を公表した新規化学物質(昭和54年6月30日以降に労働安全衛生法の新規化学物質として届け出され、官報に公示された物質)です。
なお、昭和54年2月5日の告示に基づき、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質及び日本薬局方第8改正(昭和46年)に収載された物質は安衛法においても既存化学物質として取り扱われます。これらの物質については化審法の欄の「労働安全衛生法公表化学物質に関する注記」に記載されています。
通し番号
上記(1)の物質と、上記(2)の物質のそれぞれの通し番号です。
「職場のあんぜんサイト」でハイフン付き枝番号(例:2219-2)で記載されている場合は、小数の形式(例:2219.2)で表示しています。
「職場のあんぜんサイト」でハイフン付き枝番号(例:2219-2)で記載されている場合は、小数の形式(例:2219.2)で表示しています。
安衛法官報整理番号
公表化学物質の構造について、12項目に大分類し、さらに各大分類した物質を適宜数項目に中分類して付された番号です。
安衛法官報公示時期
各物質が官報に公示された年月日です。ただし、上記(1)の物質については、官報公示日にかかわらず昭和54年6月30日としています。
官報公示名称
労働安全衛生法、又は化審法の規定により公示された化学物質の名称です。
詳細情報
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の当該化学物質の情報へのリンクです。
注記
当該化学物質にかかわるその他の情報もしくは注意事項です。
安衛法:製造等が禁止される有害物等
データ掲載日:2018.06.05(2018.04.06公示)
製造等が禁止される有害物等は、労働者に重度の健康障害が生じるものとして、労働安全衛生法第五十五条に基づき、政令第十六条第一項に定められた製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているものです。
政令番号
法第五十五条に基づき、政令第十六条第一項により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令第十六条第一項により定められた物質の名称です。
対象となる範囲(重量%)
製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
安衛法:製造の許可を受けるべき有害物
データ掲載日:2018.06.05(2018.04.06公示)
製造の許可を受けるべき有害物は、労働者に重度の健康障害が生じるおそれのあるものとして、労働安全衛生法第五十六条に基づき、政令第十七条別表第三第一号で指定され、製造前に厚生労働大臣の許可を得ることが義務付けられたものです。
政令番号
法第五十六条第一項に基づき、政令第十七条別表第三第一号により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令第十七条別表第三第一号により定められた物質の名称です。
対象となる範囲(重量%)
製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
安衛法:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
データ掲載日:2023.11.28(2023.08.30公布)
名称等を表示すべき危険物及び有害物(表示対象物)は、労働者に危険が生じるおそれのあるものもしくは労働者に健康障害が生じるおそれのあるものとして、労働安全衛生法第五十七条に基づき、政令第十七条別表第三第一号及び第十八条で指定され、譲渡又は提供する際に容器又は包装に所定の表示をすることが義務付けられたものです。
名称等を通知すべき危険物及び有害物(通知対象物)は、労働者に危険が生じるおそれのあるものもしくは労働者に健康障害が生じるおそれのあるものとして、労働安全衛生法第五十七条の二に基づき、政令第十七条別表第三第一号及び第十八条の二別表第九で指定され、譲渡又は提供する際に文書(SDS)の交付が義務付けられたものです。
平成28年6月1日施行された改正労働安全衛生法施行令により、表示対象物と通知対象物は粉状でない金属を除き同一となりました。NITE-CHRIPでは、「名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物」としてまとめて掲載しています。
なお、令和4年2月24日に公布され、令和6年4月1日から施行される改正労働安全衛生法施行令で追加された234の表示対象物と通知対象物については、施行日を付して掲載しています。
名称等を通知すべき危険物及び有害物(通知対象物)は、労働者に危険が生じるおそれのあるものもしくは労働者に健康障害が生じるおそれのあるものとして、労働安全衛生法第五十七条の二に基づき、政令第十七条別表第三第一号及び第十八条の二別表第九で指定され、譲渡又は提供する際に文書(SDS)の交付が義務付けられたものです。
平成28年6月1日施行された改正労働安全衛生法施行令により、表示対象物と通知対象物は粉状でない金属を除き同一となりました。NITE-CHRIPでは、「名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物」としてまとめて掲載しています。
なお、令和4年2月24日に公布され、令和6年4月1日から施行される改正労働安全衛生法施行令で追加された234の表示対象物と通知対象物については、施行日を付して掲載しています。
政令番号
政令第十七条別表第三第一号並びに政令第十八条及び第十八条の二別表第九により定められた物質に付与された番号です。
政令名称
政令第十七条別表第三第一号並びに政令第十八条及び第十八条の二別表第九により定められた物質の名称です。
表示(又は通知)の対象となる範囲(重量%)
製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
安衛法:がん原性物質(安衛則)(作業記録等の30年保存対象物質)
データ掲載日:2023.07.31 (2023.03.01更新/厚労省HP)
がん原性物質(安衛則)は、労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づき、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めたものです。
「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存すること等が義務付けられています。
対象物質を労働安全衛生規則別表第2に規定する通知の裾切値以上含むものが対象となります。ただし、エタノール、特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条の3に規定する特別管理物質は除かれます。また、事業者が当該物質を臨時に取り扱う場合は、作業記録等の30年間保存の対象から除かれます。
「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存すること等が義務付けられています。
対象物質を労働安全衛生規則別表第2に規定する通知の裾切値以上含むものが対象となります。ただし、エタノール、特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条の3に規定する特別管理物質は除かれます。また、事業者が当該物質を臨時に取り扱う場合は、作業記録等の30年間保存の対象から除かれます。
GHS分類名称
「国によるGHS分類」における化学物質の名称です。
適用日
本規定が適用される日が表示されます。
GHS分類における発がん性区分
「国によるGHS分類」における発がん性区分が表示されます。
対象となる範囲(重量%)
「がん原性物質」が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
備考
対象物質に関する補足情報が表示されます。「法令名称」と記載がある場合、「安衛法:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(ラベル表示・SDS交付義務対象物質)」の「政令名称」を指します。
詳細情報
各物質のNITE統合版GHS分類結果にリンクします。
安衛法:化学物質による健康障害防止のための濃度の基準(濃度基準値設定物質)
データ掲載日:2024.01.30(2023.04.27告示)
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び濃度の基準を掲載しています。
事業者は、厚生労働大臣が定める物を製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。
短時間濃度基準値が天井値として定められている場合は、この値はいかなる短時間の暴露においても超えてはならない基準値です。
事業者は、厚生労働大臣が定める物を製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。
短時間濃度基準値が天井値として定められている場合は、この値はいかなる短時間の暴露においても超えてはならない基準値です。
通し番号
厚労省HPのリストに並び順をそろえるため、NITEで付した番号
物の種類(物質名)
告示により定められた物の種類(物質名)
備考
物質名に付随した注意事項
八時間濃度基準値
一日の労働時間のうち八時間ばく露における物質濃度の各測定の測定時間による加重平均値をこれ以下とする。(温度25℃、1気圧の空気中における濃度)・(単位:ppmまたはmg/m3)
短時間濃度基準値
一日の労働時間のうち物質濃度が最も高くなると思われる十五分間のばく露濃度について各測定の測定時間による加重平均値をこれ以下とする。(温度25℃、1気圧の空気中における濃度)・(単位:ppmまたはmg/m3)
試料採取方法
技術上の指針における標準的な試料採取方法
分析方法
技術上の指針における標準的な分析方法
安衛法:皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質
データ掲載日:2024.1.30(2023.11.09更新/厚労省HP)
不浸透性の保護具等の使用義務物質には、労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行のもの)に規定された皮膚等障害化学物質等と、特化則などの特別規則において、保護具等の使用が義務づけられた物質があります。皮膚等障害化学物質等には皮膚刺激性有害物質(国が公表するGHS分類の結果等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている化学物質)と皮膚吸収性有害物質(皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質)があります。
これらの不浸透性の保護具等の使用義務物質に該当する場合は以下の項目が表示されます。
これらの不浸透性の保護具等の使用義務物質に該当する場合は以下の項目が表示されます。
通し番号
厚労省HPのリストに並び順をそろえるため、NITEで付した番号
化学物質名称
「国によるGHS分類」における物質の名称または、該当する法規制で規定された物質名称
対象物質の区分(次のいずれかが表示されます)
|
皮膚刺激性有害物質 |
国が公表するGHS分類の結果で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている化学物質です。但し特化則等で不浸透性の保護具等の使用が義務づけられている物は除かれています。 |
|
皮膚吸収性有害物質 |
皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質。但し特化則等で不浸透性の保護具等の使用が義務づけられている物を除く。 |
|
特化則等 |
化学物質関係の特別規則で、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則があげられている。 |
裾切値(重量パーセント)
皮膚等障害化学物質の含有量が裾切値未満の製剤は皮膚等障害化学物質等には該当しません。なお、特化則等の特別規則の適用を受ける化学物質については、裾切値以下の含有量の製剤については当該特別規則の適用はありません。
備考
対象物質に関する補足情報が表示されます。特別規則等に該当する場合はその規則名などが表示されます。
適用日
本規定が適用される日が表示されます。
詳細情報
各物質のNITE統合版GHS分類結果にリンクします。
安衛法:危険物
データ掲載日:2014.09.11
労働安全衛生法第十四条の規定に基づき労働安全衛生法施行令(以下、「政令」という。)第六条において労働災害を防止するため「作業主任者を選任すべき作業」が定められており、当該作業に関わる危険物及び有害物質などが政令の別表に定められています。 その別表第一に定められた物質で、「爆発性の物」、「発火性の物」、「酸化性の物」、「引火性の物」、「可燃性ガス」に分類されます。
安衛法:特定化学物質等(特化則)
データ掲載日:2023.07.31(2020.04.22公示)
労働安全衛生法施行令の別表第三で定められた化学物質等です。下記の項目を表示しています。
区分
以下のいずれかが表示されます。
|
第一類物質 |
がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高いもの。 |
|
第二類物質 |
がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの。 |
|
第三類物質 |
大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質。 |
政令番号
政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
対象となる範囲(重量%)
製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
備考
以下に該当する物質である場合に表示されます。
|
特別管理物質 |
第一類物質と第二類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質(名称、注意事項などの掲示(特化則三十八条の三)及び空気中濃度の測定結果と労働者の作業や健康診断の記録を30年間保存すること(特化則三十八条の四、四十条)等が定められている。) |
|
特定第二類物質 |
第二類物質のうち、特に漏洩に留意すべき物質 |
|
特別有機溶剤等 |
第二類物質のうち、有機則との関連があるもの |
|
オーラミン等 |
第二類物質のうち、尿路系器官にがん等の腫瘍を発生するおそれのある物質 |
|
管理第二類物質 |
第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物質 |
安衛法:鉛等/四アルキル鉛等
データ掲載日:2019.11.27
労働安全衛生法施行令の別表第四で、鉛業務として規制対象を定めていますが、そのなかで物質としての「鉛等」が定義されています。該当する場合は「該当する規則等」に「鉛中毒予防規則」と表示され、「政令名称」には「鉛等」、「備考」には「鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物」と表示されます。 なお、鉛化合物は厚生労働大臣により指定され、官報で告示されています。
また、労働安全衛生法施行令の別表第五で四アルキル鉛等業務として規制対象を定めていますが、そのなかで物質としての「四アルキル鉛」が定義されています。該当する場合は「該当する規則等」に「四アルキル鉛中毒予防規則」と表示され、政令名称には「四アルキル鉛」、備考には四アルキル鉛に該当する範囲が表示されます。
また、労働安全衛生法施行令の別表第五で四アルキル鉛等業務として規制対象を定めていますが、そのなかで物質としての「四アルキル鉛」が定義されています。該当する場合は「該当する規則等」に「四アルキル鉛中毒予防規則」と表示され、政令名称には「四アルキル鉛」、備考には四アルキル鉛に該当する範囲が表示されます。
安衛法:有機溶剤等
データ掲載日:2024.03.12(2014.08.20公布)
政令別表第六の二に定められた物質です。これらは有機溶剤中毒予防規則において、第一種有機溶剤等、第二種有機溶剤等、第三種有機溶剤等の3分類が定めら れています。有機溶剤に該当する場合は「第一種有機溶剤等」、「第二種有機溶剤等」、「第三種有機溶剤等」のいずれかの分類が表示されます。
安衛法:作業環境評価基準で定める管理濃度
データ掲載日:2022.10.11(2020.04.22公示)
作業環境評価基準(厚生労働省告示)別表に定められた濃度です。
安衛法:がん原性に係る指針対象物質
データ掲載日:2020.03.17(2020.02.07公示)
がん原性に係る指針対象物質は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものであり、労働安全衛生法第28条第3項に基づいて当該物質の名称と当該物質による労働者の健康障害を防止するための指針が公表されたものです。当該物質を製造し、又は取り扱う事業者は、労働者の健康障害を防止するために、指針に従ってばく露低減対策、作業環境測定、労働衛生教育、記録の保管、ラベルの表示・SDSの交付、等の措置を講ずることが必要です。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」がん原性に係る指針対象物質で指針を公開しています。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」がん原性に係る指針対象物質で指針を公開しています。
名称
労働安全衛生法第28条第3項に基づいて公表された物質の名称です。
詳細情報
職場のあんぜんサイトへリンクし、指針をご覧いただくことができます。
安衛法:強い変異原性が認められた化学物質
データ掲載日:2024.01.30(2023.11.30通達)
強い変異原性が認められた化学物質は、労働安全衛生法第57条の4に基づく新規届出化学物質の有害性調査及び同法第58条に基づく既存化学物質の有害性調査において強い変異原性が認められた物質で、法律に基づき通達でその物質名を公表しています。
取扱いの際は、平成5年5月17日付け基発第312号において定められた「強い変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に沿って、ばく露防止対策、作業環境測定、労働衛生教育、ラベルの表示・SDSの交付、記録の保存、等の措置を講ずることとされています。
取扱いの際は、平成5年5月17日付け基発第312号において定められた「強い変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に沿って、ばく露防止対策、作業環境測定、労働衛生教育、ラベルの表示・SDSの交付、記録の保存、等の措置を講ずることとされています。
分類
既存化学物質か新規届出化学物質のどちらであるかを示します。
名称
通達の別紙に記載の名称です。
通達日
通達の発行された年月日および通達の別紙中、物質に付与された番号です。
毒物及び劇物取締法
データ掲載日:2024.01.30(2023.05.26公示)
毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的として、1950(昭和25)年に制定された法律です。
毒物、劇物は、動物や人における知見等に基づき、「毒物劇物の判定基準」により判定され、毒物及び劇物取締法第二条 第一項(毒物)、第二項(劇物)、第三項(特定毒物)又は毒物及び劇物指定令第一条(毒物)、第二条(劇物)、第三条(特定毒物)で指定された物質です。
毒物、劇物は、動物や人における知見等に基づき、「毒物劇物の判定基準」により判定され、毒物及び劇物取締法第二条 第一項(毒物)、第二項(劇物)、第三項(特定毒物)又は毒物及び劇物指定令第一条(毒物)、第二条(劇物)、第三条(特定毒物)で指定された物質です。
| 分類 | 法律 | 政令 |
| 毒物 | 別表第一 | 第一条 |
| 劇物 | 別表第二 | 第二条 |
| 特定毒物 | 別表第三 | 第三条 |
分類
以下のいずれかが表示されます。1つの物質が複数の分類に該当する場合もあります。
| 法律・毒物/政令・毒物 | 生理的機能に危害を与える程度が激しい物質として定められています。含有率等により除外規定が個別に定められている場合もあります。 |
| 法律・劇物/政令・劇物 | 生理的機能に危害を与える程度が比較的軽い物質として定められています。含有率等により除外規定が個別に定められている場合もあります。 |
| 法律・特定毒物/政令・特定毒物 | 毒物のうち特に毒性が強く、使用法によっては人に対する危害の可能性の高い物質として定められています。 |
法律又は政令番号
法律又は政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
法律又は政令名称
法律又は政令により定められた物質の名称です。
毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの
データ掲載日:2022.04.03(2020.06.24公示)
毒物及び劇物指定令第二条(劇物)第一項第三十二号で指定された「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」から除かれる物質です。
分類
「政令・劇物・除外」が表示され、毒物及び劇物指定令第二条第一項第三十二号で定められた「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。」のうち、「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」の除外物質であることを表します。
政令番号
毒物及び劇物指定令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
名称
毒物及び劇物指定令により定められた物質の名称です。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
データ掲載日:2020.07.31(2020.06.07公示)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の的確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造・使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする法律です。
特定物質は、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令」(以下「政令」とする)で定めるものをいい、法第二条第三項に基づき、政令第三条第一項、別表一の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造及び使用の許可、輸入の承認、譲渡・譲受及び所持の制限、運搬及び廃棄等が規制されます。
なお、特定物質の塩につきましても、経済産業省のお知らせにあるように法律の対象とされていますので、ご注意ください。
第一種指定物質は、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして政令で定められた指定物質のうち、化学兵器以外の用途に使用されることが少ない物質として、法第二条第五項に基づき、政令第三条第三項、別表二の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造等予定数量の届出、製造等及び輸出入実績数量の届出等が必要になります。
第二種指定物質は、第一種指定物質以外の指定物質で、法第二条第五項に基づき、政令第三条第二項、別表三の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造予定数量の届出、製造及び輸出入実績数量の届出等が必要になります。
NITE-CHRIPでは、特定物質、第一種及び第二種指定物質について、政令により定められている物質の情報を公開していますが、法第二十九条第一項に基づき、政令第四条で指定された「有機化学物質」については公開しておりません。
例示物質に関する注意事項など詳細につきましては経済産業省のホームページ( 申告様式記入用参照資料「附表2の使用に当たっての注意事項」など)をご参照ください。
特定物質は、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令」(以下「政令」とする)で定めるものをいい、法第二条第三項に基づき、政令第三条第一項、別表一の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造及び使用の許可、輸入の承認、譲渡・譲受及び所持の制限、運搬及び廃棄等が規制されます。
なお、特定物質の塩につきましても、経済産業省のお知らせにあるように法律の対象とされていますので、ご注意ください。
第一種指定物質は、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして政令で定められた指定物質のうち、化学兵器以外の用途に使用されることが少ない物質として、法第二条第五項に基づき、政令第三条第三項、別表二の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造等予定数量の届出、製造等及び輸出入実績数量の届出等が必要になります。
第二種指定物質は、第一種指定物質以外の指定物質で、法第二条第五項に基づき、政令第三条第二項、別表三の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造予定数量の届出、製造及び輸出入実績数量の届出等が必要になります。
NITE-CHRIPでは、特定物質、第一種及び第二種指定物質について、政令により定められている物質の情報を公開していますが、法第二十九条第一項に基づき、政令第四条で指定された「有機化学物質」については公開しておりません。
例示物質に関する注意事項など詳細につきましては経済産業省のホームページ( 申告様式記入用参照資料「附表2の使用に当たっての注意事項」など)をご参照ください。
分類
以下のいずれかが表示されます。
| 特定物質(毒性物質又は原料物質) | 特定物質の毒性物質又は毒性物質の原料となる物質(原料物質)に該当することを示しています。 |
| 第1種指定物質(毒性物質又は原料物質) | 第一種指定物質の毒性物質又は毒性物質の原料となる物質(原料物質)に該当することを示しています。 |
| 第2種指定物質(毒性物質又は原料物質) | 第二種指定物質の毒性物質又は毒性物質の原料となる物質(原料物質)に該当することを示しています。 |
政令番号
政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
データ掲載日:2018.10.10(2018.08.10公示)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律は、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」(1985年採択)及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(1987年採択)」で定められた締結国の義務に加え、モントリオール議定書締約国会合での決定事項の履行を目的として、1988(昭和63)年に制定され、特定物質の製造規制並びに排出の抑制及び使用の合理化等を定めた法律です。
2016年のモントリオール議定書のキガリ改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、「特定物質代替物質」を加える等の措置を講ずる改正オゾン法「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律」が2018年7月に公布されました。
特定物質は、オゾン層を破壊するものとして、法施行令第一条第一項別表第一で定められた物質です。
特定物質代替物質は、特定物質(オゾン層破壊物質)に代替する物質で地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして、法施行令第一条第一項別表第二で定められた物質です。
NITE-CHRIPでは、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(以下「政令」とする)で定められている特定物質及び特定物質代替物質についての情報を公開しています。
2016年のモントリオール議定書のキガリ改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、「特定物質代替物質」を加える等の措置を講ずる改正オゾン法「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律」が2018年7月に公布されました。
特定物質は、オゾン層を破壊するものとして、法施行令第一条第一項別表第一で定められた物質です。
特定物質代替物質は、特定物質(オゾン層破壊物質)に代替する物質で地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして、法施行令第一条第一項別表第二で定められた物質です。
NITE-CHRIPでは、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(以下「政令」とする)で定められている特定物質及び特定物質代替物質についての情報を公開しています。
物質の種類(付属書番号-グループ)
以下のいずれかが表示されます。
| 議定書附属書AのグループI | 別表第1の1項(A-I) |
| 議定書附属書AのグループII | 別表第1の2項(A-II) |
| 議定書附属書BのグループI | 別表第1の3項(B-I) |
| 議定書附属書BのグループII | 別表第1の4項(B-II) |
| 議定書附属書BのグループIII | 別表第1の5項(B-III) |
| 議定書附属書CのグループI | 別表第1の6項(C-I) |
| 議定書附属書CのグループII | 別表第1の7項(C-II) |
| 議定書附属書CのグループIII | 別表第1の8項(C-III) |
| 議定書附属書EのグループI | 別表第1の9項(E-I) |
| 議定書附属書FのグループI | 別表第2の1項(F-I) |
| 議定書附属書FのグループII | 別表第2の2項(F-II) |
政令番号
政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
係数
議定書附属書A~C及びEのグループはオゾン破壊係数が、附属書Fのグループは地球温暖化係数が表示されます。
| オゾン破壊係数 | 政令により特定物質ごとに定められている数値です。オゾン層への影響の大きさを表す指標のひとつで、CFC-11(トリクロロフルオロメタン)1kgあたりの総オゾン破壊量を1としたときの、各化合物1kgあたりの総オゾン破壊量を表しています。 |
| 地球温暖化係数 | 政令により特定物質代替物質ごとに定められている数値です。地球温暖化への影響の大きさを表す指標のひとつで、二酸化炭素(CO2)を1とした場合の温暖化の強さを表しています。 |
大気汚染防止法
データ掲載日:2024.03.12(2020.06.05公示)
大気汚染防止法は、大気環境の保全を目的として1968(昭和43)年に制定された法律です。工場等から排出される大気汚染物質について、排出施設の種類や規模によって、物質の種類ごとに排出基準を定めています。
規制対象となる物質の種類は、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、水銀等、有害大気汚染物質、自動車排出ガスなどです。
NITE-CHRIPでは、法律、大気汚染防止法施行令(以下「政令」という。)及び中央環境審議会答申により次のように定められている物質の情報を公開しています。
なお、揮発性有機化合物(VOC)は、「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリについて 令和4年3月」、(揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ検討会)をもとに作成しています。
規制対象となる物質の種類は、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、水銀等、有害大気汚染物質、自動車排出ガスなどです。
NITE-CHRIPでは、法律、大気汚染防止法施行令(以下「政令」という。)及び中央環境審議会答申により次のように定められている物質の情報を公開しています。
なお、揮発性有機化合物(VOC)は、「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリについて 令和4年3月」、(揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ検討会)をもとに作成しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
| ばい煙(いおう酸化物) | 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、施設・地域ごとに排出基準などが定められています。 |
| ばい煙(ばいじん) | 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん(いわゆる煤)のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、施設・地域ごとに排出基準などが定められています。 |
| ばい煙(有害物質) | 物の燃焼、合成、分解、その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもので、施設・地域ごとに排出基準などが定められています。 |
| 指定ばい煙 | 工場又は事業場が集合している地域で、本法令第三条第一項、第三項又は第四条第一項の排出基準のみでは環境基本法第十六条第一項の規定による大気環境基準の確保が困難とされた地域が対象の、いおう酸化物その他の政令で定めるばい煙です。 |
| 揮発性有機化合物(VOC) |
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)で、施設ごとに排出基準などが定められています。VOC (Volatile Organic Compounds) と呼ばれています。 例示した物質は、環境省の「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ」に基づいています。 |
| 揮発性有機化合物(VOC)から除く物質 | 浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質で、大気汚染防止法の揮発性有機化合物(VOC)からは除かれる物質です。 |
| 粉じん | 物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質です。 |
| 特定粉じん | 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもので、事業場の境界基準や建築物解体時等の作業基準などが定められています。 |
| 一般粉じん | 粉じんのうち、特定粉じん以外の粉じんです。 |
| 水銀等 | 水銀に関する水俣条約の規定に基づき規制される水銀及びその化合物で、排出基準などが定められています。 |
| 自動車排出ガス | 自動車及び原動機付自転車の運行に伴い発生する、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもので、自動車種別ごとの許容限度が設定されています。 |
| 特定物質 | 物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもので、事故時における措置が定められています。 |
| 有害大気汚染物質 | 継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(法第2条第1項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)で、知見の集積等、各主体の責務が規定されています。 |
| 有害大気汚染物質(指定物質) | 有害大気汚染物質のうち、人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもので、施設ごとに抑制基準が定められています。 |
| 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質 | 中央環境審議会大気環境部会答申において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」としてリスト化された物質です。 |
| 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(優先取組物質) | 中央環境審議会大気環境部会答申において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」の中でも有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられる物質としてリスト化された物質です。 |
政令番号
政令(又は、法や答申)により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令(又は、法や答申)により定められた物質の名称です。
備考
物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
VOC排出インベントリ物質コード
「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ」記載の物質コードです。
VOC排出インベントリ物質名
「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ」記載の物質名です。
水質汚濁防止法
データ掲載日:2024.03.12(2024.01.25公示)
水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を目的として1970(昭和45)年に制定された法律です。工場等から公共用水域に排出される排出水中の有害物質の排水基準や水質汚染状況を示す項目、及び特定施設(有害物質を含む汚水又は廃液等を排出する施設)や指定施設(有害物質を貯蔵若しくは使用している施設又は指定物質を製造、貯蔵、使用若しくは処理する施設)等を設置する工場又は事業場の設置者に対する事故時の措置等を定めています。
有害物質は、カドミウムその他の人の健康に被害が生じるおそれのあるもので、水質汚濁防止法第二条第二項第一号に基づき同法施行令第二条で指定された物質です。
指定物質は、有害物質や同法第二条第五項に規定する油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、同法第二条第四項に基づき同法施行令第三条の三で指定された物質です。
油は、重油その他の政令で定める油であって、同法第二条第五項に基づき同法施行令第三条の四で指定された物質です。
NITE-CHRIPでは、水質汚濁防止法施行令(以下「政令」という。)により定められている有害物質、指定物質及び油の情報を公開しています。
有害物質は、カドミウムその他の人の健康に被害が生じるおそれのあるもので、水質汚濁防止法第二条第二項第一号に基づき同法施行令第二条で指定された物質です。
指定物質は、有害物質や同法第二条第五項に規定する油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、同法第二条第四項に基づき同法施行令第三条の三で指定された物質です。
油は、重油その他の政令で定める油であって、同法第二条第五項に基づき同法施行令第三条の四で指定された物質です。
NITE-CHRIPでは、水質汚濁防止法施行令(以下「政令」という。)により定められている有害物質、指定物質及び油の情報を公開しています。
政令番号
政令第二条(有害物質)、政令第三条の三(指定物質)及び政令第三条の四(油)により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令第二条(有害物質)、政令第三条の三(指定物質)及び政令第三条の四(油)により定められた物質の名称です。
排水基準
法第三条で定義された「排水基準」として、「排水基準を定める省令」第一条により有害物質ごとに定められた許容限度です。政令で定められた特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される排水に適用される値です。
土壌汚染対策法
データ掲載日:2023.07.31(2022.12.16公示)
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染状況の把握と、その汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることを目的として、2002(平成 14)年に制定された法律です。汚染の状況を判断するための、特定有害物質の土壌溶出量基準及び土壌含有量基準等を定めています。
特定有害物質は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法第2条第1項に基づき同法施行令第1条で指定された物質です。
土壌溶出量基準と土壌含有量基準は、土壌汚染対策法第2条第2項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(土壌汚染状況調査)で用いられる基準値です。
分解生成物とは、分解により生成するおそれのある特定有害物質です。
NITE-CHRIPでは、土壌汚染対策法施行令(以下「政令」とする)により定められている特定有害物質と、施行規則により定められている基準の情報を公開しています。
特定有害物質は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法第2条第1項に基づき同法施行令第1条で指定された物質です。
土壌溶出量基準と土壌含有量基準は、土壌汚染対策法第2条第2項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(土壌汚染状況調査)で用いられる基準値です。
分解生成物とは、分解により生成するおそれのある特定有害物質です。
NITE-CHRIPでは、土壌汚染対策法施行令(以下「政令」とする)により定められている特定有害物質と、施行規則により定められている基準の情報を公開しています。
分類
施行規則第4条第3項第2号のとおり、特定有害物質の性状から3つの分類が定められています。
第1種特定有害物質:揮発性有機化合物
第2種特定有害物質:重金属等
第3種特定有害物質:第1種及び第2種特定有害物質以外の特定有害物質(農薬等/農薬及びPCB)
第1種特定有害物質:揮発性有機化合物
第2種特定有害物質:重金属等
第3種特定有害物質:第1種及び第2種特定有害物質以外の特定有害物質(農薬等/農薬及びPCB)
政令番号
政令第1条により定められた個々の特定有害物質に付与された番号です。
政令名称
政令第1条により定められた特定有害物質の名称です。
土壌溶出量基準
地下水等経由の摂取リスクの観点から設定された、土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量で、施行規則別表4に記載された量です。
土壌含有量基準
汚染土壌を直接摂取することによる健康リスクの観点から設定された、土壌に含まれる特定有害物質の量で、施行規則別表5に記載された量です。
分解生成物
分解生成物とは、分解により生成するおそれのある特定有害物質です。
施行規則別表第1の上欄に掲げられた特定有害物質に関する採取及び測定する場合、その物質が分解することによって生成する同表下欄に掲げられた特定有害物質も採取及び測定の対象になります。
施行規則別表第1の上欄に掲げられた特定有害物質に関する採取及び測定する場合、その物質が分解することによって生成する同表下欄に掲げられた特定有害物質も採取及び測定の対象になります。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
データ掲載日:2019.03.19(2015.07.09公示)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律は、有害物質を含有する家庭用品について、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことにより、国民の健康の保護に資することを目的として、1973(昭和48)年に制定された法律です。同法は、規制の対象となる有害物質と、指定された家庭用品の基準を定めています。
規制の対象となる有害物質は、水銀化合物その他の人の健康にかかわる被害が生じるおそれのあるもので、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項に基づき、同法第二条第二項の物質を定める政令で指定されています。
規制の対象となる家庭用品は、保健衛生上の見地から、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第四条第一項に基づき、同法施行規則第一条別表等で指定されています。
NITE-CHRIPでは、家庭用品に含有される物質のうち、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令(以下「政令」とする)により定められている有害物質の情報を公開しています。
規制の対象となる有害物質は、水銀化合物その他の人の健康にかかわる被害が生じるおそれのあるもので、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項に基づき、同法第二条第二項の物質を定める政令で指定されています。
規制の対象となる家庭用品は、保健衛生上の見地から、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第四条第一項に基づき、同法施行規則第一条別表等で指定されています。
NITE-CHRIPでは、家庭用品に含有される物質のうち、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令(以下「政令」とする)により定められている有害物質の情報を公開しています。
政令番号
政令により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
家庭用品
政令にて定められた家庭用品とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第四条第一項及び第四条第二項に基づき、同法施行規則第一条、第二条で定められる別表一、別表二等に示される家庭用品です。
基準
家庭用品の基準は、施行規則第一条及び第二条で定められています。試験方法、試験機器及び試験条件等が含まれています。
食品衛生法
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(1) 基ポリマー(プラスチック)
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(1)では基ポリマー(プラスチック)の規格を定めています。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(1)では基ポリマー(プラスチック)の規格を定めています。
カテゴリ
別表第1第1表(1)に記載されているポリマーの種類です。
番号 名称
別表第1第1表(1)に記載されている通し番号と物質名です。
食品区分(酸|油|乳|酒|他)
食品区分(酸|油|乳|酒|他)及び各欄に記載の内容は下記の通りです。
| 酸 | ⅰ 酸性食品 | 食品中又は食品表面のpHが4.6以下の食品をいう |
| 油 | ⅱ 油脂及び脂肪性食品 | 食品中又は食品表面の油脂含有量が20%以上の食品をいう |
| 乳 | ⅲ 乳・乳製品 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条で規定される食品のうち、食品中又は食品表面の油脂含有量が20%未満の食品をいう |
| 酒 | ⅳ 酒類 | アルコール濃度が1体積%以上の飲料をいう |
| 他 | ⅴ その他の食品 | 上記ⅰからⅳまでに該当しない食品とする |
| ○ | 表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が、当該食品に対して使用可能であることを示す。 |
| - | 表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が、当該食品に対して使用不可であることを示す。 |
最高温度/合成樹脂区分
最高温度/合成樹脂区分及び各欄の内容は下記の通りです。
| 最高温度 | Ⅰ | 表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が使用された際に達することが許容される最高温度が70℃であることを示す。 |
| Ⅱ | 表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が使用された際に達することが許容される最高温度が100℃であることを示す。 | |
| Ⅲ | 表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が使用された際に達することが許容される最高温度が100℃を超えることを示す。 | |
| 合成樹脂区分 | 1 | ガラス転移温度若しくはボールプレッシャー温度が150℃以上のポリマー又は架橋構造を有し、融点が150℃以上のポリマー(4から7までに該当するものを除く。)に類するものであることを示す。 |
| 2 | 吸水率が0.1%以下のポリマー(1及び4から7までに該当するものを除く。)に類するものであることを示す。 | |
| 3 | 吸水率が0.1%を超えるポリマー(1及び4から7までに該当するものを除く。)に類するものであることを示す。 | |
| 4 | 塩化ビニル又は塩化ビニリデンに由来する部分の割合が50%以上のポリマーであることを示す。 | |
| 5 | エチレンに由来する部分の割合が50%以上のポリマーであることを示す。 | |
| 6 | プロピレンに由来する部分の割合が50%以上のポリマーであることを示す。 | |
| 7 | テレフタル酸及びエチレングリコールに由来する部分の割合が50mol%以上のポリマーであることを示す。 |
特記事項
別表第1第1表(1)に記載されている特記事項です。
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(2) 基ポリマー(コーティング等)
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、合成樹脂製の原材料であって、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(2)では基ポリマー(コーティング等)の規格を定めています。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(2)では基ポリマー(コーティング等)の規格を定めています。
カテゴリ
別表第1第1表(2)に記載されているポリマーの種類です。
番号 名称
別表第1第1表(2)に記載されている通し番号と物質名です。
食品区分(酸|油|乳|酒|他)及び最高温度/合成樹脂区分並びに各欄に記載の内容
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(1) 基ポリマー(プラスチック)に記載したものと同じです。
特記事項
別表第1第1表(2)に記載されている特記事項です。
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(3) 基ポリマー(微量モノマー)
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、合成樹脂製の原材料であって、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(3)では基ポリマー(微量モノマー)の規格を定めています。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(3)では基ポリマー(微量モノマー)の規格を定めています。
番号 名称
別表第1第1表(3)に記載されている通し番号と物質名です。
食品衛生法:規格基準告示別表第1第2表 添加剤
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第2表では添加剤の規格を定めています。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第2表では添加剤の規格を定めています。
番号
別表第1第2表に記載されている通し番号です。
名称
別表第1第2表に記載されている物質名です。
合成樹脂区分別使用制限(%)
第1表(1)及び(2)の表中の対応する合成樹脂区分欄に示す基ポリマーを使用して製造される器具又は容器包装に対して使用可能な量を示します。「-」は、表中の原材料が、第1表(1)及び(2)の表中の対応する合成樹脂区分欄に示す基ポリマーを使用して製造される器具又は容器包装に対して使用不可であることを示し、「*」は、表中の原材料が、第1表(1)及び(2)の表中の対応する合成樹脂区分欄に示す基ポリマーを使用して製造される器具又は容器包装に対して使用制限がないことを示します。
特記事項
別表第1第2表に記載されている特記事項です。
備考
当該物質がポジティブリスト(PLリストと略)の範囲内のものであるか確認が必要な場合に表示されます。
高圧ガス保安法
データ掲載日:2023.06.06(2022.06.22公表)
高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制することにより、
高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として、1951年(昭和26年)に制定された法律です。
NITE-CHRIPでは、法律、高圧ガス保安法施行令(以下「政令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
NITE-CHRIPでは、法律、高圧ガス保安法施行令(以下「政令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
| 高圧ガス |
「高圧ガス」とは、以下のいずれか該当するものをいいます。
一 常用の温度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガスであり、その圧力が1MPa以上であるもの又は温度35℃における圧力が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は温度15℃における圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス
四 政令で定める、温度35℃において圧力0Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガス
|
| 特定高圧ガス | 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス |
| 第1種ガス | ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気 |
| 第2種ガス | 第1種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(第3種ガス)を除く。 |
| 第3種ガス | 政令第5条表第2号における経済産業省令で定めるガス。(現在未指定) |
| フルオロカーボン及びアンモニア | フルオロカーボン(第2条第3項第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものを除く。)及びアンモニアであって、法第5条第1項第2号の規定により製造の許可を受けなければならない設備又は同条第2項第2号の規定により届出を行わなければならない設備の冷凍能力として施行令第4条の表で定める値を適用するガス |
法令等における該当条項
当該物質について規定している法律又は政令の条項等が表示されます。
法令等における名称
法律又は政令に記載されている物質の名称です。
備考
物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
高圧ガス保安法:一般高圧ガス保安規則
データ掲載日:2023.06.06(2022.06.22公表)
一般高圧ガス保安規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定しています。
NITE-CHRIPでは、一般高圧ガス保安規則(以下「省令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
NITE-CHRIPでは、一般高圧ガス保安規則(以下「省令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
| 可燃性ガス |
アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。) イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの |
| 毒性ガス | アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物 |
| 特殊高圧ガス | アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン |
| 不活性ガス | ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。) |
| 特定不活性ガス | 不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの |
法令等における該当条項
当該物質について規定している省令等の条項等が表示されます。
法令等における名称
省令に記載されている物質の名称です。
備考
物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
高圧ガス保安法:冷凍保安規則
データ掲載日:2023.07.31(2022.09.12公表)
冷凍保安規則は、1966(昭和41)年に制定された規則です。この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用する暖房を含む)に係る高圧ガスに関する保安について規定しています。
NITE-CHRIPでは、冷凍保安規則(以下「省令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
NITE-CHRIPでは、冷凍保安規則(以下「省令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
| 可燃性ガス |
アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。) イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの |
| 毒性ガス | アンモニア、クロルメチル及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物 |
| 不活性ガス | ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。) |
| 特定不活性ガス | 不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの |
| 冷媒ガス | 省令第5条第3号の表及び同条第4号の表で定める冷媒ガス |
法令等における該当条項
当該物質について規定している省令等の条項等が表示されます。
法令等における名称
省令等に記載されている物質の名称です。
備考
該当物質を含む冷媒の冷媒番号(アメリカ冷凍空調学会(ASHRAE)のStandard 34で定められた冷媒の種類を表す番号)が表示されます。
火薬類取締法
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.09公示)
火薬類取締法は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として、1950(昭和25)年に制定された法律です。
「火薬類」とは、火薬、爆薬、火工品をいい、「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であって、経済産業省令で定めるものをいいます。
NITE-CHRIPでは、火薬類取締法により次のように定められている物質の情報を公開しています。
「火薬類」とは、火薬、爆薬、火工品をいい、「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であって、経済産業省令で定めるものをいいます。
NITE-CHRIPでは、火薬類取締法により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
| 火薬 |
イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの |
| 爆薬 |
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬 ロ 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 ハ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬 ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、 テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、 ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬 ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬 ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定める もの |
| 火工品 |
イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管 ロ 実包及び空包 ハ 信管及び火管 ニ 導爆線、導火線及び電気導火線 ホ 信号焔管及び信号火せん ヘ 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。) |
| がん具煙火 | がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるもの |
法令等における該当条項
当該物質について規定している法律の条項等が表示されます。
法令等における名称
法律に記載されている物質の名称です。
容器包装の告示における品名
火薬類の容器包装の基準を定める告示に記載されている品名です。
備考
法律又は省令において、物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
国連番号、区分、容器包装方法
火薬類の容器包装の基準を定める告示(以下、この項目において「告示」という。)に記載されている国連番号、危険区分、隔離区分、容器包装方法です。
| 国連番号 | 国連危険物輸送専門家委員会が作成した「危険物輸送に関する勧告」による、輸送の際に危険性や有害性があるとされる物質又は物品の分類のために付与された4桁の数字です。国連番号が複数ある品名のものは、告示別表備考1の(2)及び(3)より定められる危険区分又は隔離区分に対応した番号が与えられています。 |
| 危険区分 | 告示により定められた危険区分です。同一の品名のもので、複数の危険区分がある場合は、JIS K4828-1(1998)、JIS K4828-2(2003)又はJIS K4828-3(1998)に規定される試験方法によって判定します。 |
| 隔離区分 | 告示により定められた隔離区分です。同一の品名のもので、複数の隔離区分がある場合は、告示別表備考1の表に定めるところにより判定します。隔離区分がN及びSの場合は、JIS K4828-1(1998)、JIS K4828-2(2003)又はJIS K4828-3(1998)に規定される試験方法によって判定します。 |
| 容器包装方法 | 告示別表備考2の表に記載されている容器包装方法の記号です。 |
消防法
消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的(法第一条)とし、1948年に制定されました。
出典
危険物等の対象物質の例は、以下の出典をもとに掲載しています。
なお、用語等を一部修正している場合があります。
「危険物災害等情報支援システム」総務省消防庁サイト
「危険物データブック2版」(編者:財団法人 東京連合防火協会、監修:東京消防庁 警防研究所)
「職場のあんぜんサイト・モデルSDS」厚生労働省サイト
なお、用語等を一部修正している場合があります。
「危険物災害等情報支援システム」総務省消防庁サイト
「危険物データブック2版」(編者:財団法人 東京連合防火協会、監修:東京消防庁 警防研究所)
「職場のあんぜんサイト・モデルSDS」厚生労働省サイト
※免責について
化学物質等が、危険物等の品名や性質等へ該当するか否かの判定は、それぞれの出典情報を元に引用したものであり、NITEが試験評価を行ったものではありません。実際の物品を取り扱う際は、事業者の責任において試験評価の上、適用運用してください。
化学物質等が、危険物等の品名や性質等へ該当するか否かの判定は、それぞれの出典情報を元に引用したものであり、NITEが試験評価を行ったものではありません。実際の物品を取り扱う際は、事業者の責任において試験評価の上、適用運用してください。
消防法:危険物
データ掲載日:2024.01.30
消防法の危険物とは、法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいいます(法第二条)。この品名欄に掲げる「その他のもので政令で定めるもの」に、危険物の規制に関する政令(以下、「危険物令」という)において品名が定められ、同等の危険性を有すると考えられる物品が指定されています。また、危険性を勘案して定められる指定数量については、この危険物令別表第三に定められています。
法令等の番号
消防法及び危険物令の条項と別表番号です。
類別 性質
法別表第一に定められた類別と性質とを合わせて記載しており、下欄のいずれかが表示されます。
| 類別 性質 | 法別表第1備考 |
| 第1類 酸化性固体 | 固体(液体(1気圧において、温度20度で液状であるもの又は温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(1気圧において、温度20度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの。 |
| 第2類 可燃性固体 | 固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すもの。 |
| 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質 | 固体又は液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの。 |
| 第4類 引火性液体 | 液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すもの。 |
| 第5類 自己反応性物質 | 固体又は液体であって、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの。 |
| 第6類 酸化性液体 | 液体であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの。 |
品名
法別表第一及び危険物令に定められた品名です。
性質
危険物令別表第三に定められた性質です。
指定数量
危険物令別表第三に定められた数量です。異なる指定数量の危険物を同一場所で貯蔵又は取り扱う場合、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上のとき、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱っているものとみなされます。
備考
対象物質に関する条件などが表示されます。
消防法:指定可燃物
データ掲載日:2024.01.30
消防法の指定可燃物とは、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして危険物の規制に関する政令(危険物令)で定められています(法第九条の四)。危険物令別表第四の品名欄に掲げる物品で、それぞれ危険性の目安となる対象となる数量が定められています。
法令等の番号
危険物令の条項と別表番号です。
品名
危険物令別表第四に定められた品名です。
対象となる数量
危険物令別表第四に定められた数量です。
備考
対象物質に関する条件などが表示されます。
消防法:消防活動阻害物質
データ掲載日:2024.01.30
消防法の消防活動阻害物質とは、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、危険物の規制に関する政令(危険物令)、危険物令別表第1及び第2のほか、総務省令で対象物質と届出の対象となる数量が定められています。
法令等の番号
危険物令及び総務省令の条項と別表番号です。
物質
危険物令又は総務省令において定められた物質です。
対象となる数量
危険物令又は総務省令において定められた数量です。
外国法規制情報
危険物リスト(国連番号/危険分類)
データ掲載日:2024.01.30(2023年度改訂23版)
本勧告は、技術的進歩、新しい物質及び材料の出現、現代の輸送システムの要請、特に、人、財産及び環境の安全確保の必要性に鑑み、国連経済社会理事会の危険物輸送専門家会議によって策定されました。危険物の輸送に係わる本勧告は、「危険物輸送に関するモデル規則」の形式で付属書として提示されています。
NITE-CHRIPでは、国連勧告・モデル規則の危険物リストに掲載された危険物の国連番号、クラス又は区分、品名及び内容、参考和訳、副次的危険性、UN容器等級を公開しています。
NITE-CHRIPでは、国連勧告・モデル規則の危険物リストに掲載された危険物の国連番号、クラス又は区分、品名及び内容、参考和訳、副次的危険性、UN容器等級を公開しています。
国連番号
危険物リストの物質又は物品ごとに付与された4桁の数字(国連番号)です。国連番号は原則として危険物の制定順の通し番号であって、番号自体に特別な意味はありませんが、番号がある物質は危険有害性があるとの判断を行うことができます。また、いくつかの国連番号は欠番になっているため、連番になっていない場合があります。
Class or division
危険物を以下に示すような9種のクラス(Class)に分類し、さらに区分(Division)を設けています。
| クラス1 | 火薬類 | |
| 区分1.1 | 一斉爆発の危険性を有する物質及び物品 | |
| 区分1.2 | 一斉爆発の危険性はないが、飛散危険性を有する物質及び物品 | |
| 区分1.3 | 一斉爆発の危険性はないが、火災の危険性及び小規模な爆発性もしくは小規模な飛散危険性のいずれか又は両方の危険性を有する物質及び物品 | |
| 区分1.4 | 重大な危険性を示さない物質及び物品 | |
| 区分1.5 | 一斉爆発の危険性を有するが、極めて鈍感な物質 | |
| 区分1.6 | 一斉爆発の危険性はなく、極めて鈍感な物品 | |
| クラス2 | ガス類 | |
| 区分2.1 | 引火性ガス | |
| 区分2.2 | 非引火性、非毒性ガス | |
| 区分2.3 | 毒性ガス | |
| クラス3 | 引火性液体 | |
| クラス4 | 可燃性固体、自然発火性物質、水と接して引火性ガスを発生する物質 | |
| 区分4.1 | 可燃性固体、自己反応性物質及び鈍化爆発物 | |
| 区分4.2 | 自然発火性物質 | |
| 区分4.3 | 水と接して引火性ガスを発生する物質 | |
| クラス5 | 酸化性物質及び有機過酸化物 | |
| 区分5.1 | 酸化性物質 | |
| 区分5.2 | 有機過酸化物 | |
| クラス6 | 毒物及び感染性物質 | |
| 区分6.1 | 毒物 | |
| 区分6.2 | 感染性物質 | |
| クラス7 | 放射性物質 | |
| クラス8 | 腐食性物質 | |
| クラス9 | 環境有害性物質を含むその他の危険な物質及び物品 | |
Name and Description
危険物の品名とその性状等です。品名は主に大文字で、性状等が品名の後に小文字で表現されます。なお、N.O.S.は Not otherwise specified.(他に品名が明示されているものを除く。)の略語です。
副次的危険性
危険物には複数の危険性を有する場合があり、主な危険性(クラス)以外の危険性につけられるのが副次危険性です。
UN容器等級
危険性の程度に応じて3つの容器等級に割り当てられます。
| 容器等級Ⅰ | 高い危険性を有する物質 |
| 容器等級Ⅱ | 中程度の危険性を有する物質 |
| 容器等級Ⅲ | 低い危険性を有する物質 |
参考和訳
「Name and Description」を字訳主体に和訳したものです。
HSコード 第6部「化学工業(類似の工業を含む。)の生産品」
データ掲載日:2023.01.31(2022年版)
HSコードとは、国際貿易を容易化するために製品の分類を標準化したコードシステム(Harmonized Commodify Description and Coding System)です。このコードシステムは1988年に世界税関機構(WCO)によって開発され、現在200以上の国や地域で使用されています。HSコードは様々な種類の商品分類を統一し、国際貿易の促進と貿易コストの削減を目的としています。
HSコードは約5,300種類の製品を21の「部(Section)」に大分類し、さらに99の「類(Chapter)」に細分化しました。その中の98類および99類は各国の自由裁量となっておるため内容は各国ごとに異なります。具体的な分類内容は世界関税機構(WCO)のウェブサイトに記載されています。
HSコードは6桁の数字で構成され、最初の2桁は「類」、中2桁は細分化された「項(Heading)」、最後の2桁はさらに細分化された「号(Sub-heading)」を示します。国際上は6桁で通用しますが、HSコードを採用した国は10桁までの数字を使用することができます。
WCOのHSコード委員会は5~6年ごとにHSコードを修正し、最新の改正案は2022年版です。
化学物質や化学製品はHSコードにおける第6部「化学工業(類似の工業を含む。)の生産品」に属しており、28類から38類までの11類を含んでいます。無機化学品と有機化学品は一般に第28類と第29類に分類されます。複数の化学品を含む混合物については使用用途に基づき第30類から第38類に分類されます。
NITE-CHRIPでは第28類と第29類のリストについて掲載しています。
HSコードは約5,300種類の製品を21の「部(Section)」に大分類し、さらに99の「類(Chapter)」に細分化しました。その中の98類および99類は各国の自由裁量となっておるため内容は各国ごとに異なります。具体的な分類内容は世界関税機構(WCO)のウェブサイトに記載されています。
HSコードは6桁の数字で構成され、最初の2桁は「類」、中2桁は細分化された「項(Heading)」、最後の2桁はさらに細分化された「号(Sub-heading)」を示します。国際上は6桁で通用しますが、HSコードを採用した国は10桁までの数字を使用することができます。
WCOのHSコード委員会は5~6年ごとにHSコードを修正し、最新の改正案は2022年版です。
化学物質や化学製品はHSコードにおける第6部「化学工業(類似の工業を含む。)の生産品」に属しており、28類から38類までの11類を含んでいます。無機化学品と有機化学品は一般に第28類と第29類に分類されます。複数の化学品を含む混合物については使用用途に基づき第30類から第38類に分類されます。
NITE-CHRIPでは第28類と第29類のリストについて掲載しています。
類
HSコードの最初の2桁によって示される「類(Chapter)」の番号です。
類の名称
HSコードにおける「類(Chapter)」で定めている名称です。
項
HSコードの中の2桁によって示される「項(Heading)」を含む4桁の番号です。
項の名称
HSコードにおける「項(Heading)」で定めている品目名称です。
HSコード
6桁で示されるHSコードの番号です。
品目名称
HSコードが示している品目の名称です。
ストックホルム条約(POPs条約)
データ掲載日:2021.11.30(2020.12.3発効)
詳細はPOPsのホームページをご覧ください。
POPs(ストックホルム)条約は、「残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants:POPs)に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on POPs)」の訳と略であり、残留性有機汚染物質の環境放出の低減、廃絶等に取り組むために、国際的な枠組みとして、2001年に採択され、2004年に発効した条約です。
POPs条約では、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が強く、長距離移動性が懸念される残留性有機汚染物質の製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定しています。
NITE-CHRIPでは、条約の付属書A、B及びCに記載された物質の名称及び官報で公表された情報を公開しています。
POPs(ストックホルム)条約は、「残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants:POPs)に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on POPs)」の訳と略であり、残留性有機汚染物質の環境放出の低減、廃絶等に取り組むために、国際的な枠組みとして、2001年に採択され、2004年に発効した条約です。
POPs条約では、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が強く、長距離移動性が懸念される残留性有機汚染物質の製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定しています。
NITE-CHRIPでは、条約の付属書A、B及びCに記載された物質の名称及び官報で公表された情報を公開しています。
付属書
以下のいずれかが表示されます。1つの物質が、複数の付属書に該当する場合もあります。
| A | 付属書 Aで記載されている物質で、各締結国は生産・使用・輸出入の廃絶の措置を講じる必要等があります(除外規定あり)。 |
| B | 付属書 Bで記載されている物質で、各締結国は生産・使用・輸出入を制限(マラリア対策のみ許可)する必要等があります。 |
| C | 付属書 Cで記載されている物質で、各締結国は非意図的生成物の放出の低減及び廃絶のための措置を講じる必要等があります。 |
条約記載名称
付属書に記載されている物質名称です。
ロッテルダム条約(PIC条約)
データ掲載日:2024.03.12(2023.10.22発効)
詳細はPICのホームページをご覧ください。
PIC(ロッテルダム)条約は、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関 するロッテルダム条約(The Rotterdam Convention on PIC(Prior Informed Consent)」の訳と略で、先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤が開発途上国に制限なく輸出されることを防ぐことを目的として、締約国間の輸出における事前通報同意(PIC)手続き等を設けた条約です。1998年に採択され、我が国では、2004(平成16)年に発効しました。
NITE-CHRIPでは、PIC手続の対象となる同条約の附属書Ⅲに掲げる化学物質に関し、輸出貿易管理令に基づく「化学物質の輸出承認について」において公表された情報を公開しています。
PIC(ロッテルダム)条約は、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関 するロッテルダム条約(The Rotterdam Convention on PIC(Prior Informed Consent)」の訳と略で、先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤が開発途上国に制限なく輸出されることを防ぐことを目的として、締約国間の輸出における事前通報同意(PIC)手続き等を設けた条約です。1998年に採択され、我が国では、2004(平成16)年に発効しました。
NITE-CHRIPでは、PIC手続の対象となる同条約の附属書Ⅲに掲げる化学物質に関し、輸出貿易管理令に基づく「化学物質の輸出承認について」において公表された情報を公開しています。
カテゴリー
附属書Ⅲに掲げる化学物質に関する条約上の用途分類をいい、以下のいずれかが表示されます。
| Pesticide | 駆除剤 |
| Pesticide formulation |
駆除用製剤 駆除剤として使用するために調製された化学物質であって、その使用の条件の下で、一回又は二回以上の暴露の後、短期間に観察され得る著しい影響を健康又は環境に及ぼすもの |
| Industrial | 工業用化学物質 |
条約記載名称
附属書Ⅲに記載されている物質名称です。
東南アジア諸国連合(ASEAN)
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)法規制情報
データ掲載日:2020.03.17
日ASEAN化学物質管理データベース(ASEAN-Japan Chemical Safety Database : AJCSD)は、日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)化学ワーキンググループ(WG-CI)の合意に基づき、日本とASEAN各国が共同で構築したデータベースです。NITEが運用機関となって、2016年4月28日より正式に運用しています。
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)法規制情報は、AJCSDにカンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの各国政府から直接提供された化学物質の規制情報が掲載されている場合、以下の項目が表示されます。
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)法規制情報は、AJCSDにカンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの各国政府から直接提供された化学物質の規制情報が掲載されている場合、以下の項目が表示されます。
詳細情報
「to AJCSD」をクリックすると、AJCSDの該当する物質のページにリンクします。
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)GHS関連情報
データ掲載日:2020.03.17
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)GHS関連情報は、AJCSDにカンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの各国政府から直接提供されたGHS関連情報が掲載されている場合、以下の項目が表示されます。
詳細情報
「to AJCSD」をクリックすると、AJCSDの該当する物質のページにリンクします。
欧州連合(EU)
ECインベントリ
データ掲載日:2024.03.12(2017.08.11更新)
ECインベントリは2008年に欧州委員会共同研究センターにより公表された、以下の3つのリストよりなる化学物質の名簿です。
①欧州既存商業化学物質名簿(EINECS)
・EC番号 (2xx-xxx-xx, 3xx-xx-xx)
「危険物質指令」(67/548/EEC)により、1971/01/01から1981/09/18の間に、欧州連合(EU)域内で流通(上市)していると考えられたおよそ10万種の化学物質をリスト化したものです。
②欧州届出化学物質リスト(ELINCS)
・ EC番号 (4xx-xxx-xx)
「危険物質指令」(67/548/EEC)により、1981/09/18から2008/05/31の間に、欧州連合(EU)域内で商業的に利用可能であった、およそ5,000の届出新規物質(NONS)をリスト化したものです。
③もはやポリマーとはみなされない物質(NLP)のリスト
・EC番号 (5xx-xxx-xx)
1992年の「危険物質指令」(67/548/EEC)の改正によりポリマーの定義が変わり、これまではポリマーであるために規制から除外されていた物質の一部が、もはやポリマーとはみなされない物質となりました。もはやポリマーとはみなされない物質のリストは、このような物質のうち、1981/09/18から1993/10/31の間に欧州連合(EU)域内で商業的に利用可能であった物質より構成されています。
NITE-CHRIPでは、このリストに記載されている物質についての情報を公開しています。
①欧州既存商業化学物質名簿(EINECS)
・EC番号 (2xx-xxx-xx, 3xx-xx-xx)
「危険物質指令」(67/548/EEC)により、1971/01/01から1981/09/18の間に、欧州連合(EU)域内で流通(上市)していると考えられたおよそ10万種の化学物質をリスト化したものです。
②欧州届出化学物質リスト(ELINCS)
・ EC番号 (4xx-xxx-xx)
「危険物質指令」(67/548/EEC)により、1981/09/18から2008/05/31の間に、欧州連合(EU)域内で商業的に利用可能であった、およそ5,000の届出新規物質(NONS)をリスト化したものです。
③もはやポリマーとはみなされない物質(NLP)のリスト
・EC番号 (5xx-xxx-xx)
1992年の「危険物質指令」(67/548/EEC)の改正によりポリマーの定義が変わり、これまではポリマーであるために規制から除外されていた物質の一部が、もはやポリマーとはみなされない物質となりました。もはやポリマーとはみなされない物質のリストは、このような物質のうち、1981/09/18から1993/10/31の間に欧州連合(EU)域内で商業的に利用可能であった物質より構成されています。
NITE-CHRIPでは、このリストに記載されている物質についての情報を公開しています。
EC番号
ECインベントリで付与された番号です。
EC名称
ECインベントリに記載されている名称です。
説明
EC名称の詳細な説明です。
Substance Infocard
ECHA(欧州化学機関)のWEBサイトで公開されている「Substance Infocards」へリンクします。ECHAのWEBサイトの利用についてはECHAのLeagal Noticeをご参照ください。
ECHA名称
ECインベントリに記載されているECHAによる名称です。EC名称と一致する場合は表示されません。
REACH:高懸念物質(SVHC)
データ掲載日:2024.03.12(認可対象リスト: 2022.04.11/候補リスト: 2024.01.23公表)
高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)は、EU加盟国又は欧州化学品庁(ECHA)がREACH規則に基づき、以下の性質を持つ物質から、選択したものです。
(a) 発がん性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(b) 変異原性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(c) 生殖・発生毒性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(d) PBT(Persistent, Bio-accumulative and Toxic)難分解性、蓄積性、毒性
(e) vPvB(very Persistent and very Bio-accumulative)難分解性と蓄積性が極めて高い
(f) 上記以外に人健康や環境に重大な影響が起こりうる科学的な証拠があり、(a)~(e)と同等の懸念を引き起こす物質
高懸念物質(SVHC)として特定された物質は、REACH規則の附属書XIVの認可リスト(Authorisation List)に加えられ、認可の対象となります。候補リスト(Candidate List)に収載されている物質は最終的に、認可リスト(Authorisation List)に登録される高懸念物質(SVHC)の候補です。
NITE-CHRIPでは、 ECHAのWEBサイトで公表されているCandidate ListとREACH規則の附属書XIVの認可リスト(Authorisation List)に記載されている物質名称等の情報を公開しています。
(a) 発がん性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(b) 変異原性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(c) 生殖・発生毒性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(d) PBT(Persistent, Bio-accumulative and Toxic)難分解性、蓄積性、毒性
(e) vPvB(very Persistent and very Bio-accumulative)難分解性と蓄積性が極めて高い
(f) 上記以外に人健康や環境に重大な影響が起こりうる科学的な証拠があり、(a)~(e)と同等の懸念を引き起こす物質
高懸念物質(SVHC)として特定された物質は、REACH規則の附属書XIVの認可リスト(Authorisation List)に加えられ、認可の対象となります。候補リスト(Candidate List)に収載されている物質は最終的に、認可リスト(Authorisation List)に登録される高懸念物質(SVHC)の候補です。
NITE-CHRIPでは、 ECHAのWEBサイトで公表されているCandidate ListとREACH規則の附属書XIVの認可リスト(Authorisation List)に記載されている物質名称等の情報を公開しています。
EC番号
欧州で化学物質に付与されるコードです。
ステータス
認可対象リストに登録されると「Authorisation List」、高懸念物質候補リストに収載されると「Candidate List」と表示されます。
物質名称
認可対象リスト、及び、高懸念物質候補リストに掲載された名称です。
説明
当該物質についての説明です。
メンバー物質名称
グループエントリーされた物質で、各々リストに掲載された名称です。
候補理由
高懸念物質候補リストに掲載された理由です。上記(a)~(f)いずれかの性質を有します。
固有の有害性
認可対象リストに登録された固有の有害性です。上記(a)~(f)いずれかの性質を有します。
収載日
企業は、候補リストに収載された日より法的義務を負うことになります。これらの義務は、リストアップされた物質自体または混合物だけでなく、成形品に含まれている物質にも及びます。
サンセット日
認可対象物質として登録されるとサンセット日が設定されます。指定されている申請日より前に認可申請が提出され、免除が適用されるか、認可が付与されない限り、市場への投入およびその物質の使用が禁止される日付です。
詳細情報
「ECHAサイトへ」をクリックすると、ECHAサイトで公表されている物質のリストを見ることができます。
EU:CLP調和分類
データ掲載日:2024.01.30(ATP20 2023.07.11 公表、2024.01.05 改正公表)
EU(European Union :欧州連合)の「物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008」(CLP規則)は、国際的に調和された分類・表示のシステム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS)に基づいており、高レベルの健康及び環境保護並びに物質や混合物などの自由な移動を確保することを目的に、有害物質又は混合物の分類及び表示、包装を適切に行うことを求めています。CLP規則の付属書VIは、有害物質の調和化された分類及び表示を定めています。
NITE-CHRIPでは、CLP規則の付属書VI表3 で公表されている有害性物質の分類に関する情報を公開しています。
なお、分類及び備考で表示される参照記号(*、****)はそれぞれ以下のことを指しています。
NITE-CHRIPでは、CLP規則の付属書VI表3 で公表されている有害性物質の分類に関する情報を公開しています。
なお、分類及び備考で表示される参照記号(*、****)はそれぞれ以下のことを指しています。
・参照記号*:有害物質が「危険物指令」(指令 67/548/EEC) に基づく特定の濃度限界値を持つことを示しており、CLP規則の分類に直接対応しません。
・参照記号****:十分なデータが入手できないため物理的ハザードを正確に分類設定できなかった危険物であり、物理的ハザードの正確な分類は試験によって確認する必要があります。
Index番号
先頭の3桁の数字は特徴を最もよく示す元素の原子番号又は分子中の有機グループに対応しています。
EC番号
ECインベントリで付与された番号です。
Chemical Name
附属書VI パート3の表3に収載されている化学物質の名称です。
個別物質名称
Chemical Nameに複数の化学物質が記載されている場合、当該CHRIP_ID及びCAS RNに対応する物質の名称が表示されます。
分類
CLP規則の付属書 I に定められたクライテリアに基づき、ハザードクラス及びカテゴリー/等級/タイプを示すコードの形式で表されています。
濃度限界値、M-ファクター
特定の濃度限界値やM-ファクターが記されています。
注記、適用条件等
CLP規則の付属書VI表3 で公表されている有害性物質の分類に関する情報です。特に注意すべき物質及び混合物の識別、分類、表示に関する注意事項が示されます。Note A~Xは物質に関する注意事項です。Note 1~12は混合物に関する注意事項です。該当する場合、注記、適用条件等の詳細へリンクします。
米国:有害物質規制法(TSCA)
TSCAインベントリ
データ掲載日:2024.03.12(2024.02更新)
米国有害物質規制法(TSCA)は「Toxic Substances Control Act」の訳と略で、人の健康及び環境を損なう不当なリスクをもたらす化学物質及び混合物を規制することにより、その影響を防止することを目的として、1976年に制定された法律です。
TSCAインベントリは、TSCA第8条(b)に基づき、米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency ; US EPA )が作成した米国内で製造・輸入又は加工されている既存化学物質のリストです。このリストに掲載されていない化学物質は「新規化学物質」とみなされ、製造前届出(Premanufacture Notice ; PMN)規制の対象となります。
NITE-CHRIPでは、最新の公表のリスト(製造業者等により秘密であると主張される部分が除かれたもの)に掲載されている化学物質についての情報を公開しています。
TSCAインベントリは、TSCA第8条(b)に基づき、米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency ; US EPA )が作成した米国内で製造・輸入又は加工されている既存化学物質のリストです。このリストに掲載されていない化学物質は「新規化学物質」とみなされ、製造前届出(Premanufacture Notice ; PMN)規制の対象となります。
NITE-CHRIPでは、最新の公表のリスト(製造業者等により秘密であると主張される部分が除かれたもの)に掲載されている化学物質についての情報を公開しています。
TSCA名称
TSCAの既存物質名簿に記載されている名称(原則的に、CAS Index Name)です。
DEF
クラス2の物質で、”Preferred CA Index Names”がその物質自体やその物質が属するカテゴリーを明確に識別できるほど具体的または完全でない場合に、その物質を識別するための重要な情報を表示します。
UVCB
"UVCB "が表示されている場合、その物質がUVCBグループのクラス2の物質、すなわち "組成不明 "、"組成変動"、"複雑な反応生成物"または"生体物質 "であることを示します。これらの物質には、明確な分子式表現がなく、構造式もないかまたは部分的にしか存在しません。
FLAG
EPA TSCA規制 Flagが表示されます。詳細は、英文説明を参照してください。
ACTIVITY
商用利用の状況が表示されます。
TSCA:重要新規利用規則(SNUR)
データ掲載日:2024.03.12(2024/02/16発効、2024/01/11公表)
詳細はEPAのホームページをご覧ください。
TSCA:重要新規利用規則(SNUR)は、「Significant New Use Rule」)の訳と略で、新規化学物質の規制において、申請者に対する同意指令(Consent Order)に加え、申請者以外の者にも同様の規制を行うために、TSCA第5条(a)項(2)号に基づき公布される規則です。
申請者に発せられる同意指令は化学物質のリスクが明確に評価できないにもかかわらず、人の健康や環境に過度のリスクをもたらすおそれや、相当な量の環境への排出もしくは人への暴露のおそれがある場合に発せられ、リスク評価に十分なデータがそろうまで、製造等を制限するものです。SNURは、公平性の観点から、この化学物質を取り扱う全事業者に対して、同意指令と同等の制限を課すことが目的です。
NITE-CHRIPではTSCA第5条(a)項(2)号に基づき公布される規則に掲載された化学物質についての情報を公開しています。
TSCA:重要新規利用規則(SNUR)は、「Significant New Use Rule」)の訳と略で、新規化学物質の規制において、申請者に対する同意指令(Consent Order)に加え、申請者以外の者にも同様の規制を行うために、TSCA第5条(a)項(2)号に基づき公布される規則です。
申請者に発せられる同意指令は化学物質のリスクが明確に評価できないにもかかわらず、人の健康や環境に過度のリスクをもたらすおそれや、相当な量の環境への排出もしくは人への暴露のおそれがある場合に発せられ、リスク評価に十分なデータがそろうまで、製造等を制限するものです。SNURは、公平性の観点から、この化学物質を取り扱う全事業者に対して、同意指令と同等の制限を課すことが目的です。
NITE-CHRIPではTSCA第5条(a)項(2)号に基づき公布される規則に掲載された化学物質についての情報を公開しています。
Section番号
40 CFR part 721, Subpart Eに収載されているSNURのSection番号です。
SNUR名称
40 CFR part 721 Subpart Eに記載されている規制対象となる化学物質の名称です。規制対象となる化学物質の名称が総称名称表示の場合には、化学物質名称の末尾に(generic)の表示が付されます。
詳細情報
「to CFR site」をクリックすると、該当するSectionのページにリンクします。
TSCA:化学物質及び混合物の優先度付け、リスク評価並びに規制
データ掲載日:2024.03.12(2023.08.29発効)
TSCA:化学物質及び混合物の優先度付け、リスク評価並びに規制は、TSCA第6条の規定に基づき、化学物質及びその混合物の製造、輸入、加工、流通、廃棄又はそれらの組み合わせが人の健康や環境に不当なリスクをもたらす又はおそれがあると結論するに足る正当な根拠がある場合に行われる規制です。
米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency ; US EPA )は、代替物利用の可能性を考慮し、負担が最も少ない要件を用いて、「製造、加工、流通の禁止」「製造、加工、流通の量の制限」などの、リスク低減に向けた適切な措置を適用します。
NITE-CHRIPでは以下の物質を公開しています。
・TSCAインベントリに掲載された化学物質のうちTSCA第6条の対象となる化学物質
・TSCA 6条に記載されている物質
・官報又はCode of Federal Regulations(CFR)にTSCA6条の対象である旨明示されている物質
なお、PCBについては、EPAが公開しているPCB Congeners、PCB Homologs、PCB Mixtures and Trade Names(Aroclor)記載の化学物質を掲載しています。
米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency ; US EPA )は、代替物利用の可能性を考慮し、負担が最も少ない要件を用いて、「製造、加工、流通の禁止」「製造、加工、流通の量の制限」などの、リスク低減に向けた適切な措置を適用します。
NITE-CHRIPでは以下の物質を公開しています。
・TSCAインベントリに掲載された化学物質のうちTSCA第6条の対象となる化学物質
・TSCA 6条に記載されている物質
・官報又はCode of Federal Regulations(CFR)にTSCA6条の対象である旨明示されている物質
なお、PCBについては、EPAが公開しているPCB Congeners、PCB Homologs、PCB Mixtures and Trade Names(Aroclor)記載の化学物質を掲載しています。
CFR番号
関連するCode of Federal Regulationsの番号が表示されます。
法規制等における名称
TSCA 第6条またはCode of Federal Regulationsによる物質名、総称名または規制名が表示されます。
化学物質名
法規制等における名称に紐付く対象となる個々の化学物質名が表示されます。
備考
Code of Federal RegulationsのPart名と補足情報が表示されます。
中国:危険化学品目録(2015版)
データ掲載日:2017.04.18(2015.02.27公示)
中国:危険化学品目録は、中国「危険化学品安全管理条例」(国務院第591号令)第3条により、害毒、腐食、爆発、燃焼、助燃等の性質を有し、人体、施設、環境に対して危険有害性を有する劇毒化学品及びその他の化学品を示します。安全監督局、産業情報技術部、公安部、環境保護部、交通運輸部、農業部、国家衛生委員会、品質検査局、鉄道管理局、民間航空局の関連10部門の同意により、作成されています。
NITE-CHRIPでは、NRCC (National Registration Center for Chemicals)のホームページで掲載されている情報(http://hxp.nrcc.com.cn/laws_chemicals_detail.html?id=1)をNITEで翻訳し、名称等を日本語で表示しています。
なお、名称中の但し書きにある「A型希釈剤」および「B型希釈剤」はそれぞれ以下のものを指しています。
NITE-CHRIPでは、NRCC (National Registration Center for Chemicals)のホームページで掲載されている情報(http://hxp.nrcc.com.cn/laws_chemicals_detail.html?id=1)をNITEで翻訳し、名称等を日本語で表示しています。
なお、名称中の但し書きにある「A型希釈剤」および「B型希釈剤」はそれぞれ以下のものを指しています。
・A型希釈剤:有機過酸化物と相容し、沸点が150℃を下回らない有機液体を指します。A型希釈剤は、すべての有機化酸化物に対する鈍性化に用いることができます。
・B型希釈剤:有機過酸化物と相容し、沸点が150℃を下回るが60℃は下回らず、引火点が5℃を下回らない有機液体を指します。B型希釈剤は、すべての有機化酸化
物に対する鈍性化に用いることができるが、沸点は、50 kgの包装物の自己加速分解温度(SADT)より少なくとも60℃高くなければなりません。
番号
『危険化学品目録』中の化学品の通し番号です。
品名
『危険化学品目録』中の品名をNITEで和訳した名称です。
別名
『危険化学品目録』中の別名をNITEで和訳した名称です。「品名」以外のその他名称を指し、一般名、慣用名等も含まれます。
備考
劇毒化学品の場合、「劇毒」と表示されます。
韓国:化評法(K-REACH)/化管法:有害化学物質、重点管理物質
データ掲載日:2023.11.28(2023.08.01公示)
韓国の化学物質管理の基礎になっていた有害化学物質管理法は、新規及び既存化学物質の登録・評価と有害化学物質の指定に関わる「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」と有害化学物質の管理に関わる「化学物質管理法(化管法)」とに改編され、2015年1月1日より施行されました。
NITE-CHRIPでは、有害化学物質(有毒物質、制限物質、禁止物質及び事故警戒物質)と重点管理物質を公開しています。
NITE-CHRIPでは、有害化学物質(有毒物質、制限物質、禁止物質及び事故警戒物質)と重点管理物質を公開しています。
番号
各カテゴリの表に記載された番号等です。
対象となる範囲(%)
混合物が規制対象となる場合の含有範囲です。
カテゴリ
以下のいずれかが表示されます。
| カテゴリ | 定義等 |
| Toxic Substance(s) | 有毒物質 化管法に基づく有害物質の取扱基準を遵守するほか、輸入時の環境部長官への申告などが必要です(化管法第20条)。 |
| Restricted Scubstance(s) | 制限物質 化評法で指定される物質であり、特定用途での取扱が禁止されます。輸入時の環境部長官の許可(化管法第20条)及び輸出時の環境部長官の承認が必要です(化管法第21条)。 |
| Prohibited Substance(s) | 禁止物質 化評法で指定される物質であり、試験用等の試薬を除いて取扱が禁止されます(化管法第18条)。 |
| Accident Precaution Chemical | 事故警戒物質 化管法で指定される物質であり、事故警戒物質の管理基準の遵守(化管法第40条)、危害管理計画書の作成・提出(化管法第41条)等が必要です。 |
| Priority Control Substances | 重点管理物質 化評法で指定される物質であり、製品に含有された重点管理物質の申告(化評法第32条)、製品内含有化学物質の情報提供(化評法第35条)が必要です。 |
化学物質名称
告示「有毒物質の指定」及び「制限物質・禁止物質の指定」の別表、化管法施行規則別表10、告示「重点管理物質の指定」の別表1及び別表2で指定された物質の名称です。
韓国:化評法(K-REACH):既存化学物質
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.01公示)
化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法/K-REACH)では、既存化学物質を年間1トン以上製造又は輸入しようとする場合は、登録が必要です。NITE-CHRIPでは、既存化学物質(1991年2月2日前に流通)と既存化学物質(1991年2月2日以後に有害性審査)の両方を掲載しています。
番号
告示「既存化学物質の一部改正」の別表に記載されたKE番号です。
カテゴリ
以下のいずれかが表示されます。
| カテゴリ | 定義等 |
| Existing Chemical Substances (Domestically distributed commercial purpose before February 2, 1991.) | 既存化学物質(1991年2月2日前に流通) 1991年2月2日前に国内で商業用として流通された化学物質として環境部長官が雇用労働部長官と協議して告示した化学物質です。(化評法第2条3.イ) |
| Existing Chemical Substances (Has undergone hazard review after February 2, 1991.) | 既存化学物質(1991年2月2日以後に有害性審査) 1991年2月2日以降、従前の「有害化学物質管理法」により有害性審査を受けた化学物質として環境部長官が告示した化学物質です。(化評法第2条3.ロ) |
化学物質名称
告示「既存化学物質の一部改正」の別表1、2で指定された物質の名称です。
備考
水和物等の情報が表示されます。
韓国:化評法(K-REACH):その他
データ掲載日:2019.06.04(2018.12.28公示)
化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法/K-REACH)では、既存化学物質について製造・輸入前の登録を求めています。事前に申告すれば数量ごとに登録猶予期間が認められますが、特定のものについては独自の登録猶予期間が設けてられています。NITE-CHRIPでは、登録対象既存化学物質、CMR物質及び登録又は申告免除化学物質を公開しています。
番号
各カテゴリの表に記載された番号等です。
カテゴリ
以下のいずれかが表示されます。
| カテゴリ | 定義等 |
| Phase-in substance(s) subject to registration (by June 30, 2018) | 登録対象既存化学物質 化評法で既存化学物質の中から指定された物質であり、年間1トン以上の製造・輸入に際して製造・輸入前に登録が必要です。登録猶予期間は2018年6月30日で終了しました。 |
| CMR Substances (shall be registered by December 31, 2021) | CMR物質 人または動物にがん、突然変異、生殖能力異常を引き起こす又は引き起こす恐れがある既存化学物質として化評法で指定される物質であり、2021年12月31日まで登録猶予期間が設けられています。 |
| Chemical Substances Exempted from Registration or Notification | 登録又は申告免除化学物質 既存化学物質のうち、化評法下で登録又は申告が免除される化学物質です。自然に存在する物質等、別表1に定める化学物質とブドウ糖、澱粉等別表2で定める化学物質があります。 |
化学物質名称
告示「登録対象既存化学物質」及び告示「’21年までに登録しなければならないがん、突然変異、生殖能力異常を引き起こす又は引き起こす恐れがある既存化学物質」の別表、並びに告示「登録又は申告免除対象化学物質」の別表1及び2で指定された物質の名称です。
備考
水和物の情報が表示されます。
注記
該当物質にかかわるその他の情報が表示されます。
台湾:TCCSCA/OSHA:既存化学物質
データ掲載日:2022.01.25(2020.11)
台湾における新規化学物質と既存化学物質の申請・登録は、環境保護署(EPA)所管の「毒性及び懸念化学物質管理法」及び関連規則の「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(以下、登録弁法と略)」に基づきますが、新規化学物質については、労働部(MOL)所管の「職業安全衛生法」及び関連規則の「新規化学物質登記管理弁法(以下、登記弁法と略)」でも規定されています。
台湾では、新規化学物質及び年間100kg以上製造又は輸入しようとする既存化学物質について登録が必要です。
既存化学物質インベントリは、MOL及びEPAによって所管されており、登録弁法と登記弁法の登録制度に基づいて作成されたリストです。2015年1月1日の発効後、2015年9月8日に増補版が発効されました。
NITE-CHRIPでは、既存化学物質インベントリに登録された物質のうちCAS登録番号を有しているものを公開しています。
台湾では、新規化学物質及び年間100kg以上製造又は輸入しようとする既存化学物質について登録が必要です。
既存化学物質インベントリは、MOL及びEPAによって所管されており、登録弁法と登記弁法の登録制度に基づいて作成されたリストです。2015年1月1日の発効後、2015年9月8日に増補版が発効されました。
NITE-CHRIPでは、既存化学物質インベントリに登録された物質のうちCAS登録番号を有しているものを公開しています。
英語名称
登録弁法及び登記弁法に基づく、既存化学物質インベントリに対応している英語名称です。
台湾:TCCSCA:標準登録既存化学物質
データ掲載日:2019.07.31(2019.03.11公表)
毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)及び関連規則である新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(以下、登録弁法と略)では、既存化学物質を年間100kg以上製造又は輸入しようとする場合は、登録が必要です。
標準登録既存化学物質は、既存化学物質の登録状況に基づいて、登録弁法で指定された物質です。標準登録既存化学物質の製造又は輸入に際しては、2020年1月1日からより詳細な毒性等の情報の登録申請が必要であり、取扱量などに応じて期限が定められています。
標準登録既存化学物質は、既存化学物質の登録状況に基づいて、登録弁法で指定された物質です。標準登録既存化学物質の製造又は輸入に際しては、2020年1月1日からより詳細な毒性等の情報の登録申請が必要であり、取扱量などに応じて期限が定められています。
期別/序列番号
登録弁法のもとで標準登録既存化学物質に付与された番号です。
英語名称
登録弁法に基づく、標準登録既存化学物質リストに掲載されている英語名称です。
中国語名称
登録弁法に基づく、標準登録既存化学物質リストに掲載されている中国語名称です。
台湾:TCCSCA:毒性化学物質
データ掲載日:2019.07.31(2019.01.16公表)
毒性及び懸念化学物質管理法は、1986年発効の毒性化学物質管理法が改定・名称修正されて、毒性化学物質及び懸念化学物質からの環境汚染や人健康への悪影響を防ぎ適正に管理することを目的に、2019年1月に公布されました。
毒性化学物質は、認可された事業者のみが取り扱うことができます。毒性化学物質を取り扱う者は、許可申請の上承認を得て、法律に基づく管理措置を遵守することが求められています。
毒性化学物質は、認可された事業者のみが取り扱うことができます。毒性化学物質を取り扱う者は、許可申請の上承認を得て、法律に基づく管理措置を遵守することが求められています。
管理番号/序列番号
毒性及び懸念化学物質管理法の下で、毒性化学物質に付与された番号です。
毒性分類
1~4の毒性分類に分かれており、分類ごとに求められる管理措置が異なります。
英語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、毒性化学物質リストに掲載されている英語名称です。
中国語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、毒性化学物質リストに掲載されている中国語名称です。
管制濃度
毒性化学物質が管制濃度以上の含有量の場合、管理対象毒性化学物質となります。
大量取扱基準
毒性分類1、2又は3の毒性物質に定められている基準です。取扱い総量が基準以上の場合は、許可証(製造、輸入、販売)や登記手続き(使用、貯蔵、輸出、廃棄)が求められます。基準未満の場合は、主管機関の認可を取得すると取扱いが可能となります。
備考
大量取扱基準に注釈が付いている場合、記載しています。ただし、アスベストのみ管制濃度に関する注釈です。
台湾:TCCSCA:懸念化学物質
データ掲載日:2021.03.09(2020.10.30公表)
毒性及び懸念化学物質管理法では懸念化学物質の取扱いには認可文書を取得する必要があります。濃度、量、定期的な申告等が定められており、法律に基づく管理措置を遵守することが求められています。
管理番号/序列番号
毒性及び懸念化学物質管理法の下で、懸念化学物質に付与された番号です。
英語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、懸念化学物質リストに掲載されている英語名称です。
中国語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、懸念化学物質リストに掲載されている中国語名称です。
管制濃度
懸念化学物質が管制濃度以上の含有量の場合、管理対象懸念化学物質となります。
詳細情報
「to EPA (Taiwan) site」をクリックすると、台湾EPAサイトで公表されている物質のリストと規制についての詳細情報を見ることができます。
有害性・リスク評価情報
NITE統合版GHS分類結果
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.29公開)
「NITE統合版GHS分類結果」は、「政府によるGHS分類結果」を統合し、基本的に1物質1ファイルとなるように各危険有害性項目の最新版の情報のみを掲載したものです(形態や状態等により2ファイルに分かれているものもあります)。同じ物質で複数回再分類された物質、または一部の危険有害性項目のみが再分類された物質をとりまとめ、項目ごとに最新の結果のみを掲載しています。
また、フォーマットや表記につきましては最新の日本産業規格(JIS):JIS Z 7252(日本産業規格:GHSに基づく化学品の分類方法)及び JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法(ラベル・SDS等について))を参照しております。政府による分類事業で部分的な再分類が実施されていない場合は、「政府によるGHS分類結果」と分類結果は同様で、NITEによりJIS Z 7252, Z 7253 に従った分類結果の表現、コード等に書き換えています。
なお「NITE統合版GHS分類結果」も、「政府によるGHS分類結果」と同様、事業者がラベルやSDSを作成する際の参考として公表しており、同じ内容を日本国内向けのラベルやSDSに記載しなければならないという義務はありません。
GHS関連情報及び分類事業の詳細については以下のWEBサイトをご覧ください。
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
また、フォーマットや表記につきましては最新の日本産業規格(JIS):JIS Z 7252(日本産業規格:GHSに基づく化学品の分類方法)及び JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法(ラベル・SDS等について))を参照しております。政府による分類事業で部分的な再分類が実施されていない場合は、「政府によるGHS分類結果」と分類結果は同様で、NITEによりJIS Z 7252, Z 7253 に従った分類結果の表現、コード等に書き換えています。
なお「NITE統合版GHS分類結果」も、「政府によるGHS分類結果」と同様、事業者がラベルやSDSを作成する際の参考として公表しており、同じ内容を日本国内向けのラベルやSDSに記載しなければならないという義務はありません。
GHS関連情報及び分類事業の詳細については以下のWEBサイトをご覧ください。
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
版(エディション)
政府によるGHS分類事業で再分類されることにより情報が更新された場合に値(version)が更新されます。2019年度までに公開された「政府によるGHS分類結果」をとりまとめたものがversion1です。2019年度以降に新たに新規分類として公開された物質についても同様にversion1と版(エディション)が記載されます。
公表名称
GHS分類事業において公表された各対象物質の名称です。
分類結果
各物質のNITE統合版GHS分類結果(HTML及びExcel)にリンクします。
政府によるGHS分類結果
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.29公開)
政府によるGHS分類結果は、国際的に調和された分類・表示のシステム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS )に基づき、 2006(平成 18 )年度からGHS関係各省により実施された分類事業の結果です。結果の内容は、分類結果、シンボル、注意喚起語、危険有害性情報などの情報から構成されています。GHS関連情報及び分類事業の詳細については以下のWEBサイトをご覧ください。
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
実施年度
GHS分類事業の実施年度が表示されます。
公表名称
GHS分類事業において公表された各対象物質の名称です。
分類結果
各物質のGHS分類結果(HTML及びExcel)にリンクします。
備考
複数年度の分類結果があり、一部の項目のみの分類結果しかない場合に、他の項目の分類結果の見方の補足説明が表示されます。
厚労省:GHS対応モデルラベル・モデルSDS
データ掲載日:2023.11.28(2023.08.16公開)
GHS対応モデルラベル・モデルSDSは、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS )」に基づくラベル及び安全データシート(Safety Data Sheet: SDS)の作成の参考のため、厚生労働省が作成し、厚生労働省ホームページ内の「職場のあんぜんサイト」から公表されています。
GHS対応モデルラベル・モデルSDSには、主として、関係省庁等連絡会議が作成した政府向けGHS分類ガイダンス等に基づいて分類した結果が用いられています。
GHS対応モデルラベル・モデルSDSは自由に引用又は複写いただけますが、実際に使用されるラベルやSDSに対する責任は、ラベルやSDSの作成者にあることにご留意ください。
GHS対応モデルラベル・モデルSDSには、主として、関係省庁等連絡会議が作成した政府向けGHS分類ガイダンス等に基づいて分類した結果が用いられています。
GHS対応モデルラベル・モデルSDSは自由に引用又は複写いただけますが、実際に使用されるラベルやSDSに対する責任は、ラベルやSDSの作成者にあることにご留意ください。
名称
「職場のあんぜんサイト」の「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」において公表されている物質名称です。
モデルラベル
「職場のあんぜんサイトへ」をクリックすると、「職場のあんぜんサイト」で公表されているモデルラベルにリンクします。
モデルSDS
「職場のあんぜんサイトへ」をクリックすると、「職場のあんぜんサイト」で公表されているモデルSDSにリンクします。
リレーショナル化学災害データベース(RISCAD)
データ掲載日:2018.12.04
RISCADは産業技術総合研究所(産総研)が運営する「リレーショナル化学災害データベース」です。
産総研で蓄積されてきた経済産業省所管の火薬類、高圧ガス関連の災害事例や消防法危険物関連災害事例、その他の化学プラント関連災害事例を基礎として、これらの災害事例が整理されています。
これらの中から主な事故について事象を時系列で整理し、「事故分析手法PFA」(商標登録 第5580785号)で分析した事故進展フロー図、関連化学物質の危険性情報、化学プロセスフローなどがリンクされています。
化学物質を取り扱う際の事前評価や事業現場での安全教育に活用できます。
産総研で蓄積されてきた経済産業省所管の火薬類、高圧ガス関連の災害事例や消防法危険物関連災害事例、その他の化学プラント関連災害事例を基礎として、これらの災害事例が整理されています。
これらの中から主な事故について事象を時系列で整理し、「事故分析手法PFA」(商標登録 第5580785号)で分析した事故進展フロー図、関連化学物質の危険性情報、化学プロセスフローなどがリンクされています。
化学物質を取り扱う際の事前評価や事業現場での安全教育に活用できます。
物質ID
RISCADで付与された物質IDです。
名称
RISCADに収載されている物質の名称です。
物質情報
「to RISCAD」をクリックすると、RISCADの物性情報のページにリンクします。
事故情報
「to RISCAD」をクリックすると、RISCADの事故情報のページにリンクします。
消防庁:危険物災害等情報支援システム
データ掲載日:2024.03.12(2023.02更新)
危険物災害等情報支援システムは消防庁が運営するデータベースです。消防庁で蓄積された危険物に関する物理化学的性状などが整理されています。化学物質を適切に扱うための参考情報として使用できます。
物質名
危険物災害等情報支援システムの物性概略一覧に表示された物質の名称です。危険物災害等情報支援システムに複数の名称が表示されている場合、NITE-CHRIPでは先頭に表示されている名称を掲載しています。
危険物分類
消防法の危険物確認試験のフローチャートで判定された結果を表示しています。
| カテゴリ | 定義等 |
| 危険物質 | 危険物確認試験のフローチャートに従い、消防法上の「危険物」である蓋然性が高いと判断された物質です。 |
| 非危険物質 | 危険物確認試験のフローチャートに従い、消防法上の「危険物」ではないと判断される蓋然性が高いと判断された物質です。 ※消防法上の「危険物」に該当しないだけであり、安全であることを示すわけではありません。 |
消防活動阻害物質
消防法における消防活動阻害物質に該当する場合はそのカテゴリーが表示されます。
物性概略一覧
「消防庁サイトへ」をクリックすると、危険物災害等情報支援システムの物性概略一覧のページにリンクします。
物性詳細
「消防庁サイトへ」をクリックすると、危険物災害等情報支援システムの個別物質の詳細ページにリンクします。
国内有害性評価書/リスク評価書等
化学物質有害性評価書/初期リスク評価書
データ掲載日:2009.06.30 (2009.03更新) (有害性評価書)/
〃 2009.01.29 (2008.12更新) (初期リスク評価書)/
〃 2013.04.25 (2009.05更新) (初期リスク評価書概要版)
〃 2009.01.29 (2008.12更新) (初期リスク評価書)/
〃 2013.04.25 (2009.05更新) (初期リスク評価書概要版)
化学物質有害性評価書は、文献調査等から得られた化学物質安全性情報を基に作成し、有識者からなる委員会での審議を経て公表した化学物質の評価書です。以下の3種類あります。
初期リスク評価書は、「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロジェクト」(NEDO事業)で開発した初期リスク評価手法に基づいて作成した評価書です。評価手法については、「初期リスク評価指針」(評価するための考え方)及び「初期リスク評価書作成マニュアル」(評価書作成のための具体的手順)としてまとめています。
・独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構 (NEDO) の委託事業「化学物質総合評価管理プログラム」のうち「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロジェクト」の成果物。化学物質審議会管理部会・審査部会安全性評価管理小委員会の審議を経て公表しています。
・上記プロジェクトで用いた「初期リスク評価指針」「初期リスク評価書作成マニュアル」に基づき、NITEが独自に作成した評価書。評価書の内容は、上記プロジェクトと同じ委員会にて審議しています。
・経済産業省の委託事業「平成 20年度化学物質安全確保・国際規制対策推進等(化管法指定化学物質の有害性に関する調査)」の成果物。委託事業の中で設置された有害性評価専門委員会での審議を経て公表しています。
初期リスク評価書は、「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロジェクト」(NEDO事業)で開発した初期リスク評価手法に基づいて作成した評価書です。評価手法については、「初期リスク評価指針」(評価するための考え方)及び「初期リスク評価書作成マニュアル」(評価書作成のための具体的手順)としてまとめています。
評価書番号
該当する物質の評価書が公表されている場合は、評価書番号(化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書共通の番号)が表示されます。
評価物質名称
化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書のタイトルに記載されている物質の名称です。
詳細情報
以下のファイルをPDF形式でご覧いただくことができます。
・有害性評価書
・初期リスク評価書
・初期リスク評価書概要版
また、評価書が公表あるいは更新された年月も併せて表示されます。
・有害性評価書
・初期リスク評価書
・初期リスク評価書概要版
また、評価書が公表あるいは更新された年月も併せて表示されます。
環境省化学物質の環境リスク評価結果
データ掲載日:2023.10.03 (2023.03公表)
環境省化学物質の環境リスク評価は、環境省環境保健部環境リスク評価室が、1997(平成 9)年度から、独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センターの協力を得て実施しているもので、その結果は、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価 専門委員会において審議を受け、「化学物質の環境リスク評価」としてとりまとめられ公表されています。
巻・評価の種類
「化学物質の環境リスク評価」において、該当物質が掲載されている巻数および項目です。
発行年月
該当物質が掲載されている「化学物質の環境リスク評価」の発行年月です。
評価物質名称
「化学物質の環境リスク評価」に記載されている物質の名称です。
詳細情報
環境省のWEBサイトへリンクし、公表されている該当物質の評価内容(PDF)をご覧いただくことができます。
安衛法:リスク評価実施物質
データ掲載日:2024.03.12(2024.01.31更新)
リスク評価実施物質は、労働者の健康障害防止に係るリスクの評価を行うために設置された「化学物質のリスク評価検討会」において検討されたリスク評価の結果がとりまとめられたものです。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」リスク評価実施物質でそのデータを公開しています。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」リスク評価実施物質でそのデータを公開しています。
名称
上記の「職場のあんぜんサイト」リスク評価実施物質において公表された物質名称です。
リスク評価書、初期リスク評価書、詳細リスク評価書
職場のあんぜんサイトへリンクし、公開されているリスク評価書をご覧いただくことができます。
安衛法:化学物質による災害事例
データ掲載日:2022.01.25(2021.12.13更新)
化学物質による災害事例は、労働現場で実際に起きた事故事例について、発生状況、原因、対策などをまとめています。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」化学物質による災害事例でそのデータを公開しています。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」化学物質による災害事例でそのデータを公開しています。
名称
上記の「職場のあんぜんサイト」化学物質による災害事例において公表された物質名称です。
災害事例
職場のあんぜんサイトへリンクし、公開されている災害事例をご覧いただくことができます。
化学物質安全性(ハザード)評価シート
データ掲載日:2006.09.04(2006.06更新)
化学物質安全性 (ハザード) 評価シートは、経済産業省の委託により、1996 (平成 8 )年度から2001(平成 13 )年度まで(財)化学物質評価研究機構 (CERI) が主体となって文献調査等による化学物質安全性情報を基に原案を作成し、化学物質審議会安全対策部会安全評価管理分科会の審議を経て公表した化学物質の評価文書です。
評価シート番号
該当する物質の評価シートが公表されている場合は、評価シート番号が表示されます。ハイフンの前の数字は、審議会において了承された年度(西暦)を表しています。
公表・更新年月
評価シートが公表された年月です。更新がされているシートに関しては、最新の更新日が表示されます。
評価物質名称
評価シートのタイトルに記載されている、評価物質の名称です。
詳細情報
「評価シート(PDF)」をクリックすると、評価シートをPDF形式でご覧いただくことができます。
化審法:Japanチャレンジプログラム
データ掲載日:2017.06.06
Japanチャレンジプログラムは化審法既存化学物質の安全性情報の収集を加速化するために、厚生労働省、経済産業省及び環境省と国内企業が連携して化学物質の安全性情報を収集・発信する 「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」のことです。
化学物質名称
Japanチャレンジプログラム評価対象物質の名称です。
詳細情報
化審法データベース(J-CHECK)へリンクし、公開されている評価結果をご覧いただくことができます。
国外有害性評価書/リスク評価書等
OECD:高生産量化学物質(HPV Chemicals)
データ掲載日:2016.04.07(2016.04確認)/ 日本語訳;2024.01.30(2023.11公表)
OECD:高生産量化学物質(HPV Chemicals)は、経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation Development ; OECD)加盟国において、1カ国以上で、年間の製造量が1,000トンを超える高生産量(High Production Volume ; HPV)のもので、安全性の点検を行う対象として、その名称が高生産量化学物質点検事業(HPV Chemicals Assessment Programme)の候補名簿に掲載されている物質です。同プログラムは1992年から開始され、OECD加盟先進国が、これらに該当する化学物質のハ ザードデータ・暴露データを収集し、初期評価を実施しています。同プログラムの名称は2011年に、共同化学品アセスメントプログラム (Cooperative Chemical Assessment Programme)へと改められ、評価の対象が、HPVから全化学物質に広げられました。
NITE-CHRIPでは、OECD Existing Chemicals Database において、HPV Chemicalsとして確認された物質名称等を公開しています。DatabaseのホームページではCAS登録番号(CAS RN)等の検索により、レポートの原文を見ることができます。
NITE-CHRIPでは、OECD Existing Chemicals Database において、HPV Chemicalsとして確認された物質名称等を公開しています。DatabaseのホームページではCAS登録番号(CAS RN)等の検索により、レポートの原文を見ることができます。
リスト記載名称
OECD Existing Chemicals Database において、HPV Chemicalsとして確認された名称です。
詳細情報
OECD Existing Chemicals Databaseへリンクします。
SIAP日本語訳
候補物質のうち、初期評価を行ったデータセットをSIDS(Screening Information Data Set)といい、その評価レポートをSIAR(SIDS Initial Assessment Report)といいます。
SIARの抄録をSIAP(SIDS Initial Assessment Profile)といい、最終草案として公表されているものがOECDのWEBサイトに掲載されています。
日本化学物質安全・情報センターでは、WEBサイトにこれらのSIAPの日本語訳を順次掲載しており、NITE-CHRIPで、「物質名称」をクリックするとその日本語訳にリンクします。
日本化学物質安全・情報センターでは、WEBサイトにこれらのSIAPの日本語訳を順次掲載しており、NITE-CHRIPで、「物質名称」をクリックするとその日本語訳にリンクします。
ICSC(国際化学物質安全性カード)
データ掲載日:2022.11.29(2020.07.21更新)
ICSC ( 国際化学物質安全性カード : International Chemical Safety Cards )は、欧州委員会(European Commision : EC) 協力の下、WHO (World Health Organization) と ILO (International Labour Office) により共同で行われている IPCS (国際化学物質安全性計画; International Programme on Chemical Safety )の事業で、化学物質が人の健康及び環境に与えるリスクを評価し、その情報を提供することを目的としたカードです。
ICSC は、工場、農業、建設業などの作業場で使用する化学物質の人への健康や安全に関する重要な情報を簡潔にまとめたもので、法的な拘束力を持つ文書ではないが、国際的に認められた専門家が健康や安全性に関する情報を収集、検証してまとめた標準的な用語から成り立っているカードです。
ICSCは、ILOのWEBサイトにおいて全文が公開されています。
ICSC は、工場、農業、建設業などの作業場で使用する化学物質の人への健康や安全に関する重要な情報を簡潔にまとめたもので、法的な拘束力を持つ文書ではないが、国際的に認められた専門家が健康や安全性に関する情報を収集、検証してまとめた標準的な用語から成り立っているカードです。
ICSCは、ILOのWEBサイトにおいて全文が公開されています。
ICSC番号
該当する物質のICSCが公表されている場合は、ICSC番号が表示されます。
ICSCタイトル
ICSCに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「ILOのサイトへ」をクリックするとILOのWEBサイトで公開されているICSCへリンクします。
CICADs(国際化学物質簡潔評価文書)
データ掲載日:2024.01.30(2013年No.1-78:2017.01.10日本語訳更新)
CICADs (国際化学物質簡潔評価文書)は、「Concise International Chemical Assessment Documents」 の略で、各国・地域や国際機関で作成された評価文書、又は EHC (環境保健クライテリア;Environmental Health Criteria)を基に、IPCS (国際化学物質安全性計画; International Program on Chemical Safety) が作成、出版している、リスク評価のために重要な情報を提供する評価書です。
その枠組みは以下のとおりです。
(1)国等の評価結果をベースに簡潔で国際的に有用なリスク評価を目指す。
(2)外部による批判的検討を効果的に行い、信頼性と効率を保証する。
(3)国際的調和を視野に最新のリスク評価の考え方を積極的に適用する。
この評価書は、IPCSから出版されている他、IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
その枠組みは以下のとおりです。
(1)国等の評価結果をベースに簡潔で国際的に有用なリスク評価を目指す。
(2)外部による批判的検討を効果的に行い、信頼性と効率を保証する。
(3)国際的調和を視野に最新のリスク評価の考え方を積極的に適用する。
この評価書は、IPCSから出版されている他、IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
CICADs番号
該当する物質のCICADsが出版されている場合は、CICADs番号が表示されます。
CICADsタイトル
CICADsに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「to IPCS site」をクリックするとIPCSのWEBサイトで公開されているCICADsへリンクします。
日本語訳
「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳又は全訳へリンクします。
EHC(環境保健クライテリア)
データ掲載日:2020.12.14(2020.04.12更新)/ 2012.11.12(2007.08更新)(日本語訳)
EHC (環境保健クライテリア)は「Environmental Health Criteria 」の略で、IPCS (国際化学物質安全性計画; International Program on Chemical Safety )が作成している化学物質のリスク評価文書です。この評価の対象とされる化学物質は、家庭用化学物質、大気・水・食品中の汚染物質、化粧品、食品添加物、天然毒物、工業薬品、農薬等とされており、医薬品は除外されています。
「環境保健クライテリア」の主な構成は、下記のとおりです。
・人及び環境の暴露源、環境中での移行・分布及び変化、環境濃度と人への暴露、体内動態及び代謝。
・環境中の生物への影響、人への影響、人の健康へのリスク及び環境への影響に関する評価。
この評価書は、WHOから出版されているほか、IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
「環境保健クライテリア」の主な構成は、下記のとおりです。
・人及び環境の暴露源、環境中での移行・分布及び変化、環境濃度と人への暴露、体内動態及び代謝。
・環境中の生物への影響、人への影響、人の健康へのリスク及び環境への影響に関する評価。
この評価書は、WHOから出版されているほか、IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
EHC発刊番号
該当する物質のEHCが出版されている場合は、EHC発刊番号が表示されます。
詳細情報
「IPCSサイトへ」をクリックするとIPCSのWEBサイトで公開されているEHCへリンクします。ただし、EHC発刊番号232以降については、WHOのWEBサイトで公開されているEHCへリンクします。
EHCタイトル
EHCに記載されているタイトル(物質名等)です。
日本語訳
「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳又は全訳へリンクします。
米国ATSDR(有害物質疾病登録局):Toxicological Profiles
データ掲載日:2022.05.31(2022.04.27更新)
米国 ATSDR (有害物質疾病登録局; Agency for Toxic Substances and Disease Registry):Toxicological Profiles は、ATSDR が作成した NPL(National Priorities List ;国家優先リスト)地域において検出される有害物質に対する毒性プロファイルです。NPL 地域における検出頻度、毒性及び人間に対する暴露の可能性に基づいてランク付けを行い、対象物質としています。
評価物質名称
Profileに記載されている物質名等です。
詳細情報
「to ATSDR site」をクリックすると、ATSDRのWEBサイトで公表されている該当物質のProfileへリンクします。
発行年月
該当物質が掲載されている資料の発行年月です。
備考
Addendum(補遺)の発行に関する情報です。
米国環境保護庁:IRIS(統合リスク情報システム)
データ掲載日:2023.06.06(2023.04.公表)
IRIS (米国環境保護庁統合リスク情報システム)は、「Integrated Risk Information System」 の略で、米国 EPA (環境保護庁)により運営されている、環境汚染からの人の健康影響の評価を行うプログラムです。
IRIS データベースは、化学物質による人への健康影響に関する情報(慢性非発がん性影響と個別の有害性に対する経口参照用量 (RfD) 及び吸入参照濃度 (RfC)、発がん影響に対する経口スロープファクター、経口及び吸入ユニットリスク等)を、個々の化学物質ごとに収集、提供しています。
農薬等に使用される化学物質としてIRISプログラムでは取り扱われなくなった物質は「List by Archived」で確認することができます。
IRIS データベースは、化学物質による人への健康影響に関する情報(慢性非発がん性影響と個別の有害性に対する経口参照用量 (RfD) 及び吸入参照濃度 (RfC)、発がん影響に対する経口スロープファクター、経口及び吸入ユニットリスク等)を、個々の化学物質ごとに収集、提供しています。
農薬等に使用される化学物質としてIRISプログラムでは取り扱われなくなった物質は「List by Archived」で確認することができます。
公表物質名称
IRISで公表されている評価物質名です。
詳細情報
「to EPA site」をクリックすると、IRIS(EPAのWEBサイト)で公表されている該当物質の情報へリンクします。
米国環境保護庁:AEGLs(急性ばく露ガイドライン濃度)
データ掲載日:2020.01.28
AEGLs(急性ばく露ガイドライン濃度)は、空気中に多くの化学物質が偶発的もしくは意図的に放出された緊急時に対応するために、健康影響が発生する可能性のある空気中の化学物質の濃度を表したものです。健康影響の大きさによって、レベル1-3に分かれています。
レベル1:著しい不快感、炎症や無症状の非感覚的な影響があるが、そこまで深刻ではなく一時的な影響にすぎないレベル。
レベル2:体の状態が元に戻らず、長期的に健康影響を与えるレベル。
レベル3:生命を脅かすまたは死につながるレベル。
レベル1:著しい不快感、炎症や無症状の非感覚的な影響があるが、そこまで深刻ではなく一時的な影響にすぎないレベル。
レベル2:体の状態が元に戻らず、長期的に健康影響を与えるレベル。
レベル3:生命を脅かすまたは死につながるレベル。
化学物質名称
AEGLsで公表されている化学物質名です。
ステータス
以下のステータスが表示されます。
| Final | 米国研究評議会や米国科学アカデミー(NRC/NAS)で公表されたものです。 |
| Interim | 「Proposed」のパブリックコメントに関する米国諮問委員会のレビュー後に決定されたものです。「Interim」は、NRC / NASによるピアレビュー後、「Final」が公開されるまでに、組織で使用できるようになっています。最終値が公表される前に、暫定値の変更が行われることがあります。 また、場合によっては、修正された暫定値がEPAのウェブサイトに掲載される場合があります。 |
| Proposed | NAC / AEGL委員会によるAEGLsドラフトがレビュー及び同意された後、パブリックコメントのために連邦官報に掲載されているものです。 |
| Holding Status Chemicals | NAC / AEGL委員会によって審査されており、AEGLs値を決定するデータが不十分なため保留中のものです。 |
AEGL値
「to EPA site」をクリックすると、AEGLs(EPAのWEBサイト)で公表されている該当物質の情報へリンクします。
EU(欧州連合):リスク評価書
データ掲載日:2016.11.29(2014.11更新)/ 2018.12.04(2018.11.06更新)(日本語訳)
EU (European Union ;欧州連合):リスク評価は、REACH にかかわる欧州議会 (European Parliament) 及び欧州理事会規則(EC)1907/2006 に基づいて実施され、評価書は、ECHA (European chemicals Agency;欧州化学品庁) から公表されています。リスク評価は、1990 年から 1994 年までに年間 1,000t 以上製造又は輸入された化学物質 (HPVChemicals) 及び 10~1,000t の間で製造又は輸入された化学物質 (LPV Chemicals) について、データを収集し、人や環境に影響を与える可能性がある物質として作成された優先リストに基づいて、実施されています。
この評価書は、ECHAのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
この評価書は、ECHAのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
EC番号
該当する物質の評価情報が、評価レポートとしてECHAのWEBサイトで公表されている場合は、その物質のEC番号が表示されます。
公表・更新
評価レポートが公表、又は更新された年月が表示されます。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「to ECHA site」をクリックすると、ECHAのWEBサイトで公表されている「Information from the Existing Substances Regulation (ESR)」のページへリンクします。
日本語訳
「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳又は全訳へリンクします。
BUA(ドイツ化学会諮問委員会):リスク評価書
データ掲載日:2022.1.25(2021.7.7更新)
BUA (ドイツ化学会諮問委員会):リスク評価書は、ドイツ連邦政府の既存化学物質のリスク評価を支援することを目的として、1982 年に GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker ;ドイツ化学会)の諮問委員会として設立された BUA が作成した評価文書です。BUA リスク評価書は、環境及び健康に有害な化学物質を規制する法案の根拠としてドイツ連邦政府に活用されています。なお、BUAは、 「Beratergremium fur Altstoffe; Advisory Committee on Existing Chemicals」の略で、1997 年に「GDCh Advisory Committee on Existing Chemicals」と改称(略称:BUA)、その活動は 2007 年に終了しています。
BUA番号
該当する物質について、BUAで評価を実施したことが報告されている場合は、BUA番号が表示されます。
物質名
評価書に記載されている物質名等です。
関係情報
「to BUA site」をクリックすると、GDChのWEBサイトへリンクします。
カナダ:優先物質リスト(PSL)
データ掲載日:2018.06.05(2013.06.21更新)
カナダ:優先物質リスト(PSL)は、カナダ環境省 ( Environment Canada ) とカナダ保健省 ( Health Canada ) が、1991 年に制定した CEPA (カナダ環境保護法; Canadian Environmental Protection Act )に基づき策定した、包括的かつ詳細なリスク評価を優先的に行う物質のリスト(優先物質リスト; Priory Substances List) です。当該リストに掲載された化学物質は、カナダ環境省と保健省がリスク評価を行い、「有害」であると判定されると、有害物質リストに掲載され、リスク管理措置が適用されます。
リストの種類
PSL1またはPSL2が表示されます。
PSL1(First Priority Substances List);1989年に公表され、44物質類が含まれます。
PSL2(Second Priority Substances List);1995年に公表され、25物質類が含まれます。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
関係情報
「to Environment Canada site」をクリックすると、カナダのWEBサイトで公表されている物質のリストを見ることができます。
オーストラリア:PEC (優先既存化学品) Assessment Reports
データ掲載日:2023.11.28(2020.05.05公表)
オーストラリア: PEC (優先既存化学品 )Assessment Report は、健康や環境への懸念に基づき、規制当局 NICNAS (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme ) が、PEC(Priority Existing Chemicals) として宣言している、オーストラリア国内で既に使用されている化学物質に関する評価書です。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「to AICIS site」をクリックするとAICISのWEBサイトで公表されている Priority Existing Chemical assessments のページへリンクします。
日本産業衛生学会
日本産業衛生学会:許容濃度
データ掲載日:2023.11.28(2023.9.25発行 2023年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防する手引きに用いることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表Ⅰ-1.許容濃度」に記載されている評価物質の名称です。
許容濃度
労働者が1日8時間、週40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、当該化学物質の平均曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。数値の後の(最大許容濃度)とは、作業中のどの時間をとっても曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。
詳細
提案理由書または許容濃度に対応する表にリンクします。詳細情報の種類と内容は以下のとおりです。
| 提案理由書 | 提案理由情報をpdfファイルでダウンロードできます。 |
| 表I-3 | 粉塵の許容濃度の表(粉塵の種類及び許容濃度)。 |
| 表III-2 | 過剰発がん生涯リスクレベルと対応する評価値 |
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表Ⅰ-1.許容濃度」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:生物学的許容値
データ掲載日:2023.11.28(2023.9.25発行 2023年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
生物学的許容値は、生物学的モニタリング値がその勧告値の範囲内であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響がみられないと判断される濃度です。
総合情報表示画面の「表Ⅱ-1」をクリックすると、「表Ⅱ-1.生物学的許容値」をpdfファイルでダウンロードできます。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表II-1.生物学的許容値」に記載されている評価物質の名称です。
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表II-1.生物学的許容値」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:発がん性分類
データ掲載日:2023.11.28(2023.9.25発行 2023年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表III-1.発がん性分類」に記載されている評価物質の名称です。
発がん分類
以下の分類で表示されます。
| 1 | [第1群]ヒトに対して発がん性があると判断できる物質 |
| 2A | [第2群A]ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質(疫学研究からの証拠は限定的であるが、動物実験からの証拠が十分な物質) |
| 2B | [第2群B]ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質(疫学研究からの証拠が限定的であり、動物実験からの証拠が十分でない物質) |
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表III-1.発がん性分類」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:感作性物質
データ掲載日:2023.11.28(2023.9.25発行 2023年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
感作性物質は気道感作性物質と皮膚感作性物質があり、気道感作性物質とは、その物質によりアレルギー性呼吸器疾患を誘発する物質とされています。皮膚感作性物質とは、その物質によりアレルギー性皮膚反応を誘発する物質とされています
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表IV.感作性物質」に記載されている評価物質の名称です。
気道
気道感作性物質の分類が表示されます。
| 1 | [第1群]ヒトに対して明らかに感作性がある物質 |
| 2 | [第2群]ヒトに対しておそらく感作性があると考えられる物質 |
| 3 | [第3群]動物試験などによりヒトに対して感作性が懸念される物質 |
皮膚
皮膚感作性物質の分類が表示されます。
| 1 | [第1群]ヒトに対して明らかに感作性がある物質 |
| 2 | [第2群]ヒトに対しておそらく感作性があると考えられる物質 |
| 3 | [第3群]動物試験などによりヒトに対して感作性が懸念される物質 |
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表IV.感作性物質」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:生殖毒性物質
データ掲載日:2023.11.28(2023.9.25発行 2023年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表V.感作性物質」に記載されている評価物質の名称です。
生殖毒性分類
男女両性の生殖機能に対して有害な影響を及ぼす作用または次世代児に対して有害な影響を及ぼす作用としています。女性では妊孕性,妊娠,出産,授乳への影響等,男性では,受精能への影響等としています。生殖器官に影響を示すものについては、上述の生殖機能への影響が懸念される場合に対象に含められます。次世代児では、出生前曝露による、または、乳汁移行により授乳を介した曝露で生じる、胚・胎児の発生・発育への影響、催奇形性、乳児の発育への影響とし、離乳後の発育、行動、機能、性成熟、発がん、老化促進などへの影響が明確な場合にも、生殖毒性として考慮します。
ともに以下の分類で表示されます。
| 1 | [第1群]ヒトに対して生殖毒性を示すことが知られている物質 |
| 2 | [第2群]ヒトに対しておそらく生殖毒性を示すと判断される物質 |
| 3 | [第3群]ヒトに対する生殖毒性の疑いがある物質 |
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表V-1.生殖毒性物質」に記載されているデータに対する注釈です。
発がん性評価
IARC(国際がん研究機関):発がん性評価
データ掲載日:2024.03.12(Vol.1-135、2023.12.06更新)
IARC (国際がん研究機関)発がん性評価は、WHO(世界保健機関)の一機関であり、人のがんの原因、発がん性のメカニズム、発がんの制御の科学的方法の開発に関する研究を行っている IARC(International Agency for Research on Cancer) が、「IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 」で公表している発がん分類の情報(発がん性グループ 1、 2A、2B、 3 )です。 個別物質の詳細な情報はモノグラフで公表されています。
https://monographs.iarc.who.int/monographs-available/
NITE-CHRIPでは、「IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans」で公表されている発がん性グループを提供しています。「公表年」の後に「online」が付記されている場合は、モノグラフは電子媒体のみで公表されています。 「公表年」の後に「In Prep.」が付記されている場合は、モノグラフは公表されていません。
「発がん性グループ」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
https://monographs.iarc.who.int/monographs-available/
NITE-CHRIPでは、「IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans」で公表されている発がん性グループを提供しています。「公表年」の後に「online」が付記されている場合は、モノグラフは電子媒体のみで公表されています。 「公表年」の後に「In Prep.」が付記されている場合は、モノグラフは公表されていません。
「発がん性グループ」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
| グループ1 |
ヒトに対して発がん性を示す このカテゴリーはヒトにおいて充分な発がん性の証拠がある物質に適用する。 例外的に、ヒトにおける発がんの証拠は充分とはいえないが、実験動物において充分な発がんの証拠があり、かつ暴露されたヒトにおいて、関連する発がんメカニズムを通してこの物質が作用するという強力な証拠がある場合にはこの物質をこのカテゴリーに入れることがある。 |
| グループ2A |
ヒトに対しておそらく発がん性を示す このカテゴリーは、ヒトにおいて発がんの証拠が限定的であり、実験動物において充分な発がんの証拠がある物質に適用する。場合によっては、ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であるが、実験動物において充分な発がんの証拠があり、かつ発がんがヒトにおいて作用するメカニズムを介して行われる強力な証拠がある場合にもこのカテゴリーに区分されることがある。 例外的に、単にヒトにおいて発がんの証拠が限定的であることを基にこのカテゴリーに分類することもあり得る。メカニズムを考慮して、類縁物質がGroup 1又はGroup2Aに分類されている物質のクラスに明らかに属するならば、その物質はこのカテゴリーに指定されることがある。 |
| グループ2B |
ヒトに対して発がん性を示す可能性がある このカテゴリーはヒトにおいて発がんの証拠が限定的であり、実験動物において発がんの証拠が充分ではない物質に適用する。ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であるが、実験動物において発がんの証拠が充分である場合にも適用する。 場合によっては、ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であり、実験動物においても発がんの証拠が決して充分ではないが、メカニズムや他のデータから発がんの証拠が示唆される物質の場合にはこのグループに入れることがある。 単にメカニズムや他の関連データからの強力な証拠に基づきこのカテゴリーに分類されることがある。 |
| グループ3 |
ヒトに対する発がん性について分類できない このカテゴリーは通常ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であり、かつ、実験動物においても証拠が不十分又は限定的な物質に適用される。 例外的に、ヒトにおいて発がんの証拠が不十分で、実験動物において充分な発がん性の証拠があるが、メカニズム的に実験動物で見られた発がんがヒトで生じないという強力な証拠がある場合このカテゴリーに入れることがある。 他のいずれのグループにも分類されない物質もまたこのカテゴリーに入れる。 Group 3の評価は非発がん性又は全面的に安全であることの判定ではない。特に暴露範囲が広がる、あるいは発がんデータに異なる解釈がある時には、多くの場合、さらなる研究を必要とする。 |
詳細情報
IARCのWEBサイトで公表されているモノグラフへリンクします。(in prep.)が付記されているモノグラフは公開されていません。
米国EPA(環境保護庁):発がん性評価
データ掲載日:2023.06.06(2023.04.10公表)
米国 EPA (環境保護庁)発がん性評価は、EPA (Environmental Protection Agency)が、IRIS(Integrated Risk Information System) の中で公表した、化学物質の発がん性の評価、分類です。1986年、1996年、1999年及び2005年のガイドラインに基づいて評価されています。
NITE-CHRIPでは、1986年、1996年、1999年及び2005年のガイドラインに基づいて評価された発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
NITE-CHRIPでは、1986年、1996年、1999年及び2005年のガイドラインに基づいて評価された発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
1986年ガイドライン
| A |
Human Carcinogen: ヒト発がん性物質 |
| B1 |
Probable human carcinogen - based on limited evidence of carcinogenicity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in animals: 限定されたヒト発がん性を示す証拠及び動物での十分な証拠に基づき、おそらくヒト発がん性物質 |
| B2 |
Probable human carcinogen - based on sufficient evidence of carcinogenicity in animals: 動物での十分な証拠に基づいて、おそらくヒト発がん性物質 |
| C |
Possible human carcinogen: ヒト発がん性がある可能性がある物質 |
| D |
Not classifiable as to human carcinogenicity: ヒト発がん性が分類できない物質 |
| E |
Evidence of non-carcinogenicity for humans: ヒト発がん性がないという証拠がある物質 |
1996年ガイドライン
| K/L |
Known/likely human carcinogen: ヒト発がん性が知られている物質/可能性が高い物質 |
| CBD |
Carcinogenic potential cannot be determined: ヒト発がん性を決定できない物質 |
| NL |
Not likely to be carcinogenic to humans: ヒト発がん性の可能性が低い物質 |
1999年ガイドライン
| CaH |
Carcinogenic to humans: ヒト発がん性物質 |
| L |
Likely to be carcinogenic to humans: ヒト発がん性の可能性が高い物質 |
| S |
Suggestive evidence of carcinogenicity, but not sufficient to assess human carcinogenic potential: ヒト発がん性を評価するには不十分だが、発がん性を示唆する物質 |
| I |
Data are inadequate for an assessment of human carcinogenic potential: ヒト発がん性評価には情報が不十分な物質 |
| NL |
Not likely to be carcinogenic to humans: ヒト発がん性の可能性が低い物質 |
2005年ガイドライン
| CaH |
Carcinogenic to humans: ヒト発がん性物質 |
| L |
Likely to be carcinogenic to humans: ヒト発がん性の可能性が高い物質 |
| S |
Suggestive evidence of carcinogenic potential: 発がん性を示唆する物質 |
| I |
Inadequate information to assess carcinogenic potential: 発がん性評価には情報が不十分な物質 |
| NL |
Not likely to be carcinogenic to humans: ヒト発がん性の可能性が低い物質 |
暴露経路
| Oral route | 経口経路で評価されたもの |
| Inhalation route | 吸入経路で評価されたもの |
| Oral route, Inhalation route | 経口経路及び吸入経路で評価されたもの |
詳細情報
「to Substance Profile」をクリックするとEPAのWEBサイトで公表されている該当物質のProfileへリンクします。
米国国家毒性計画(NTP):発がん性評価
データ掲載日:2022.04.01(第15次報告書、22021.12.21公表)
米国NTP(国家毒性計画)は、米国内における毒性試験計画の調整、毒性分野における科学的基盤の強化などを目的として、NIEHS(国立環境衛生科学研 究所:National Institute of Environmental Health Sciences)、NIOSH(国立労働安全衛生研究所:National Institute for Occupational Safety and Health)、NCTR(国立毒性研究センター:National Center for Toxicological Research)などの国立研究機関を中心に創設されたNTP(National Toxicology Program)が実施しています。NTPでは発がん性物質の分類や評価についての報告書を公表しています。
NITE-CHRIPでは、報告書(Report on Carcinogens)の中の物質リスト(Substances Listed)に記載されている化学物質の発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
NITE-CHRIPでは、報告書(Report on Carcinogens)の中の物質リスト(Substances Listed)に記載されている化学物質の発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
| Known | ヒト発がん性があることが知られている物質(Known to be Human Carcinogens) |
| RAHC | ヒト発がん性があると合理的に予測される物質(Reasonably Anticipated to be Human Carcinogens) |
| - | 評価ランクが記載されていない物質 |
NAME OR SYNONYM
米国国家毒性計画(NTP)発がん性物質第15次報告書(15th Report on Carcinogens)に記載されている物質名称です。
詳細情報
「to Substance Profile」をクリックするとNTPのWEBサイトで公表されている該当物質のProfileへリンクします。
EU(欧州連合):発がん性評価
データ掲載日:2024.01.30(ATP20 2023.07.11 公表、2024.01.05 改正公表)
EU 発がん性評価は、EU (European Union ;欧州連合)による「危険な物質の分類、包装及び表示に関する法律、規制、行政規定の近似化にかかわる理事会指令 67/548/EEC 付属書Ⅰ(危険な物質のリスト)」の分類結果でしたが、2009 年 1 月に発効した「物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008」(CLP 規則)の付属書VI に包含されました。
NITE-CHRIPでは、付属書VI のパート3で公表されている発がん性分類(発がん性のカテゴリー1A, 1B, 2)を提供しています。
「カテゴリーコード」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
NITE-CHRIPでは、付属書VI のパート3で公表されている発がん性分類(発がん性のカテゴリー1A, 1B, 2)を提供しています。
「カテゴリーコード」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
| カテゴリー1A |
ヒトに対する発がん性が知られている物質 ヒトの物質の暴露とがん発生の因果関係が確立された場合はカテゴリー1Aに分類する。 |
| カテゴリー1B |
ヒトに対しておそらく発がん性がある物質 動物に対する発がん性を実証する十分な証拠がある動物試験を根拠とする場合はカテゴリー1Bに分類する。 |
| カテゴリー2 |
ヒトに対する発がん性が疑われる物質 ヒト又は動物での調査より得られた証拠をもとに、確実にカテゴリー1A又は1Bに分類するには不十分な場合はカテゴリー2に分類する。 |
物質名称
CLP規則の付属書VIパート3記載の名称が表示されます。
Chemical Name
CLP規則のChemical Nameに記載されている名称です。物質名称と同じ場合は表示されません。
安全性要約書(JCIA BIGDr)
データ掲載日:2023.01.31
安全性要約書(JCIA BIGDr)は、自社で製造販売する化学品に関する GPS/JIPS検討結果(リスク評価結果等)をわかりやすい書式でまとめたものです。日本企業が作成したGPS安全性要約書へのリンクの一覧を掲載しています。物質名別、CAS登録番号(CAS RN)別、企業別に掲載しておりますので、日本企業が作成した安全性要約書を効率よく検索・参照することができます。
物質名称
安全性要約書(JCIA BIGDr)中の物質名称です。
詳細情報
「JCIA BIGDrのページへ」をクリックすると、JCIA BIGDrで公開している安全性要約書を見ることができます。
試験結果・試験報告書
経済産業省:化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)
データ掲載日:2024.03.12(2023.07.31公表)
化審法:化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)は、経済産業省が公表した微生物等による分解性及び魚介類の体内における蓄積性に関する以下の判定結果等です。
物質名称
経済産業省が公表した化学物質又は試験物質の名称です。
分解性の判定結果
公表内容又は判定結果が表示されます。
蓄積性の判定結果
公表内容又は判定結果が表示されます。
濃縮度試験の試験結果
濃縮倍率(BCF)の最大値又は定常状態における濃縮倍率(BCFss)の値が表示されます。
分配係数試験の試験結果
分配係数(LogPow)の値が表示されます。
詳細情報
化審法データベース(J-CHECK)へリンクし、公開されている判定結果等をご覧いただくことができます。
厚生労働省:既存化学物質安全性点検結果(毒性)
データ掲載日:2024.03.12
厚生労働省:既存化学物質安全性点検結果(毒性)は、厚生労働省が既存化学物質の安全性点検事業の一環として、国立医薬品衛生食品衛生研究所を中心に毒性試験を実施した結果です。
点検結果は、国立医薬品衛生食品衛生研究所の「既存化学物質毒性データベース」及び「既存化学物質毒性試験報告書」(1994~2006年[vol.1~vol.13]:化学物質点検推進連絡協議会発行)で公表しています。
点検結果は、国立医薬品衛生食品衛生研究所の「既存化学物質毒性データベース」及び「既存化学物質毒性試験報告書」(1994~2006年[vol.1~vol.13]:化学物質点検推進連絡協議会発行)で公表しています。
掲載巻(vol.)
「化学物質毒性試験報告書」(化学物質点検推進連絡協議会発行)に掲載されている巻数です。
点検物質名称
国立医薬品衛生研究所のWEBサイトで試験結果が公表された物質の名称です。
詳細情報
化審法データベース(J-CHECK)へリンクし、公開されている試験結果をご覧いただくことができます。
環境省化学物質の生態影響試験結果
データ掲載日:2019.11.26(2019.03公表)
環境省化学物質の生態影響試験結果は、化学物質の生態系に及ぼすリスクを評価することを目的として、環境省が水生生物(藻類、甲殻類、魚類及び底生生物)を対象に実施した既存化学物質の安全性点検です。
藻類:成長阻害試験、ミジンコ:急性遊泳阻害試験、ミジンコ:繁殖阻害試験、魚類:急性毒性試験、魚類:延長毒性試験、魚類:初期生活段階毒性試験、を実施しています。
藻類:成長阻害試験、ミジンコ:急性遊泳阻害試験、ミジンコ:繁殖阻害試験、魚類:急性毒性試験、魚類:延長毒性試験、魚類:初期生活段階毒性試験、を実施しています。
物質名称
試験結果が公表された物質の名称です。
詳細情報
化審法データベース(J-CHECK)へリンクし、公開されている試験結果をご覧いただくことができます。
安衛法:がん原性試験実施結果
データ掲載日:2023.06.06(2023.05.10更新)
がん原性試験とは、複数(ラット、マウス)の動物種に対して化学物質をほぼ生涯(2年間)投与(吸入ばく露、経口投与)し、臓器の変化等によりその化学物質のがん原性を調べるものであり、安衛法第57条の5に基づき厚生労働省が実施しているものです。厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」がん原性試験実施結果でそのデータを公開しています。
NITE-CHRIPでは、上記の「職場のあんぜんサイト」でがん原性試験結果が公表されている物質の名称とその調査結果の概要を提供しています。
NITE-CHRIPでは、上記の「職場のあんぜんサイト」でがん原性試験結果が公表されている物質の名称とその調査結果の概要を提供しています。
化学物質名称
上記の「職場のあんぜんサイト」がん原性試験結果の概要において公表された物質名称です。
概要
職場のあんぜんサイトへリンクし、公開されているがん原性試験結果(吸入試験結果又は経口投与試験結果)の概要をご覧いただくことができます。
安衛法:変異原性試験結果
データ掲載日:2016.04.07(2015.10.01確認)
既存化学物質の変異原性試験結果は、労働安全衛生法第五十七条の五に基づき、厚生労働省が行っているものであり、厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」変異原性試験結果でそのデータを公開しています。
NITE-CHRIPでは、上記の「職場のあんぜんサイト」で変異原性試験結果が公表されている物質の名称とその調査結果を提供しています。
NITE-CHRIPでは、上記の「職場のあんぜんサイト」で変異原性試験結果が公表されている物質の名称とその調査結果を提供しています。
化学物質名
上記の「職場のあんぜんサイト」変異原性試験結果において公表された物質名称です。名称の末尾に(気体)とあるものは、ガス暴露法によって試験されています。
試験結果
以下のいずれかが表示されます。
| 微生物を用いた変異原性試験(エームズ試験)結果 | 陰性、陽性、陰性/陽性(陰性と陽性の両方の結果がある場合) |
| CHL/IU細胞を用いた染色体異常試験結果 | 陰性、陽性、擬陽性(判定不能の場合) |
経済産業省による安全性試験結果
データ掲載日:2015.12.17(2013.07.31公表)
経済産業省による安全性試験結果は、経済産業省が安全性情報収集・整備のために実施した毒性試験結果です。その内容はNITEに設置したハザードデータ評価委員会において専門家の評価を受けています。
試験物質名称
試験を行った物質の名称が表示されます。
試験名
実施した試験名が表示されます。
詳細情報
化審法データベース(J-CHECK)へリンクし、公開されている試験結果をご覧いただけます。
NITE安全性試験結果
データ掲載日:2016.05.31(2004.10.18公表)
NITE安全性試験結果は、厚生労働省の「化審法/既存化学物質安全性点検(毒性)」又は環境省の「化学物質の生態影響試験」において実施されていない物質を対象として、NITEが独自に実施した毒性試験・生態毒性試験結果です。本試験結果はNITEが設置したハザードデータ評価委員会が評価したものです。
試験物質名称
毒性試験、生態毒性試験を行った物質の名称が表示されます。
毒性試験
該当する物質の毒性試験が行われている場合は、化審法データベース(J-CHECK)へリンクし、公開されている試験結果をご覧いただけます。
生態毒性試験
該当する物質の生態毒性試験が行われている場合は、化審法データベース(J-CHECK)へリンクし、公開されている試験結果をご覧いただけます。
経済産業省:内分泌かく乱作用に関する試験結果及び有害性評価書
データ掲載日:2007.03.30
内分泌かく乱作用によってもたらされる有害影響(毒性)については、適切なリスク評価に基づき効果的に対応していくことが重要です。内分泌かく乱作用に関する試験結果及び有害性評価書は、経済産業省の化学物質審議会審査部会・管理部会の内分泌かく乱作用検討小委員会を中心に実施された、「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」と指摘された化学物質の試験結果と有害性の評価文書です。
内分泌かく乱作用検討小委員会等では、内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の選別・評価に必要な試験法の開発及びそのデータの取得などを行っています。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/naibunpi.html
NITE-CHRIPでは試験方法開発の過程で得られたデータ及び有害性評価書を公開しています。
内分泌かく乱作用検討小委員会等では、内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の選別・評価に必要な試験法の開発及びそのデータの取得などを行っています。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/naibunpi.html
NITE-CHRIPでは試験方法開発の過程で得られたデータ及び有害性評価書を公開しています。
公表物質名称
有害性評価書に記載された物質名称、又は、試験が実施された物質の名称が表示されます。
試験結果
試験結果および有害性評価書のページにリンクします。掲載されている試験内容等は以下の通りです。
[受容体結合試験(RBA)]
ヒトエストロゲン受容体 (hER) α及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の結合親和性と天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの結合親和性を比較した相対結合親和性(=RBA;Relative Binding Affinity)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF):RBA値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
ヒトエストロゲン受容体 (hER) α及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の結合親和性と天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの結合親和性を比較した相対結合親和性(=RBA;Relative Binding Affinity)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF):RBA値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
[レポーター遺伝子アッセイ(PC50))]
ヒトエストロゲン受容体(hER) α-安定形質転換系、ヒトエストロゲン受容体(hER)β-一過性発現系及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)-一過性発現系のアゴニスト活性に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の遺伝子転写活性を天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの最大転写活性化倍率と比較して50%を示す試験物 質の濃度(=PC50)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF):PC50値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
ヒトエストロゲン受容体(hER) α-安定形質転換系、ヒトエストロゲン受容体(hER)β-一過性発現系及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)-一過性発現系のアゴニスト活性に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の遺伝子転写活性を天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの最大転写活性化倍率と比較して50%を示す試験物 質の濃度(=PC50)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF):PC50値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
[子宮増殖アッセイ]
雌のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の子宮重量等を比較してホルモン様作用(エストロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗エストロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。 影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF):試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
雌のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の子宮重量等を比較してホルモン様作用(エストロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗エストロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。 影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF):試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
*上記試験結果のうち、平成14年、平成15年度に実施した一部の試験結果については、値のみの表示となります。当該試験のグラフについては整備が完了次第公表する予定です。
[ハーシュバーガーアッセイ]
雄のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の副生殖器重量等を比較してホルモン様作用(アンドロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗アンドロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。 影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF):試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
雄のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の副生殖器重量等を比較してホルモン様作用(アンドロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗アンドロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。 影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF):試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
[改良28日間反復投与試験、子宮内・経乳汁暴露試験]
現在試験データを整理中であり、NITE-CHRIPで順次公開する予定です。
現在試験データを整理中であり、NITE-CHRIPで順次公開する予定です。
[2世代繁殖毒性試験]
化学物質に暴露された親世代の影響がどのように子や孫に及ぶのかを調べる試験です。該当する物質の報告書が公表されている場合には「報告書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の2世代繁殖試験の報告書をご覧いただくことができます。
化学物質に暴露された親世代の影響がどのように子や孫に及ぶのかを調べる試験です。該当する物質の報告書が公表されている場合には「報告書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の2世代繁殖試験の報告書をご覧いただくことができます。
[有害性評価書]
経済産業省内分泌かく乱作用検討小委員会においてとりまとめられた有害性評価書です。該当する物質の評価書が公表されている場合には「評価書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の有害性評価書をご覧いただくことができます。
経済産業省内分泌かく乱作用検討小委員会においてとりまとめられた有害性評価書です。該当する物質の評価書が公表されている場合には「評価書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の有害性評価書をご覧いただくことができます。
米国NTP(国家毒性計画):長期試験レポート
データ掲載日:2023.10.03(2023.03.10, 2023.07.05公表)
米国 NTP (国際毒性計画):長期試験レポートは、米国内における毒性試験計画の調整、毒性分野における科学的基盤の強化などを目的として、NIEHS (国立環境衛生科学研究所; National Institute of Environmental Health Sciences )、NIOSH (国立労働安全衛生研究所; National Institute for Occupational Safety and Health )、NCTR (国立毒性研究センター; National Center for Toxicological Research )などの米国の国立研究機関を中心に創設された NTP (National Toxicology Program) が公表した、化学物質の長期毒性及び発がん性試験レポートです。
NTPでは、その他にも短期毒性試験、遺伝子改変動物を用いた毒性試験、免疫毒性試験、発生毒性試験、飲料水に関する毒性試験、多世代生殖試験、エイズ治療薬に関する毒性試験等のレポートを公表しており、それらについては NTPサイトからアクセスが可能です。
NTPでは、その他にも短期毒性試験、遺伝子改変動物を用いた毒性試験、免疫毒性試験、発生毒性試験、飲料水に関する毒性試験、多世代生殖試験、エイズ治療薬に関する毒性試験等のレポートを公表しており、それらについては NTPサイトからアクセスが可能です。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
概要
「to NTP site」をクリックするとNTPのWEBサイトで公表されている該当物質のAbstractへリンクします。
詳細情報
「to NTP site」をクリックするとNTPのWEBサイトで公表されている該当物質のFull Textのファイルへリンクします。
DBRP:微生物特性情報
データ掲載日:2023.10.3
NITEバイオテクノロジーセンター(NBRC)では、生物資源データプラットフォーム(DBRP:Data and Biological Resource Platform)を運営しています。DBRPでは、NBRCが保有する生物資源(NBRC株、RD株)に関する情報に加えて、物質生産や薬剤耐性などの特性情報や文献情報、およびゲノムなどのオミックス情報といった様々な情報を掲載しています。
詳しくはDBRPとは(DBRPのページへリンクします)をご参照ください。
NITE-CHRIPでは、DBRPで公開されている情報のうち、化学物質に関連する特性(物質の生産、分解など)を有する微生物属性情報へのリンクを掲載しています。
詳しくはDBRPとは(DBRPのページへリンクします)をご参照ください。
NITE-CHRIPでは、DBRPで公開されている情報のうち、化学物質に関連する特性(物質の生産、分解など)を有する微生物属性情報へのリンクを掲載しています。
化合物名
特性の対象となる化合物名が表示されます。
特性の種類
特性の種類(生産、分解など)が表示されます。
詳細情報
DBRPに掲載されている微生物属性情報のページへリンクします。ページ下部には「このデータにリンクしている情報」としてDBRP内における関連情報へのリンクが表示され、ここから微生物株の情報など様々な情報がご覧いただけます。